お役立ちコラム
正義感が強すぎる子どもは発達障害?「正義感」の背景にある本当の理由と接し方
2025.07.24公開 / 2025.09.03更新

園や学校の集団行動において、子どもの正義感が強すぎることで、指摘して自分が不利になったり、危険な目に遭う可能性があったり、過度にお友達に注意してトラブルになるなど、心配が尽きないという方もいるのではないでしょうか。
子どもの行動や心配ごとの要因を「正義感が強いから」と一言でまとめてしまうと、その背景にある要因やサインを見逃してしまうリスクもあります。
「正義感」というのはあくまで周囲からの評価であり、子ども自身は「正義」を前提に行動しているというよりも、親や先生に教わった「ルール」に従って行動しているだけ、というケースも多くあるからです。
この記事では、これらの前提を踏まえて、正義感が強すぎるお子さまの心理や背景を解説し、具体的な対応をご紹介します。
この記事を書いている会社:
株式会社LITALICO
LITALICOジュニアは、発達が気になるお子さま向けソーシャルスキル&学習教室です。
指導実績45,000人以上※1、 全国190教室以上※2、多くの指導実績を通して培ったノウハウに基づき、満足度の高いサービスを提供しています。
2024年8月時点(児童発達支援・放課後等デイサービス・パーソナル総数)
2024年9月時点(児童発達支援・放課後等デイサービス・パーソナル総数)
幅広いニーズと困りごとへの指導実績!
ADHD/自閉スペクトラム症/学習障害/グレーゾーン/言葉の遅れ/感情コントロールが苦手/コミュニケーションが苦手/学習の遅れ
「正義感が強すぎる」とはどのような状態?

皆さんがお子さまの「正義感が強すぎる」と感じる場面とは具体的にどのような場面でしょうか。
例えば、他の子のルール違反を許せず注意してしまったり、弱い立場の友達を助けようと率先して仲裁に入るなど、ルールや道徳感に準じて考えると一見正しい行動であることが多いのではないでしょうか。
しかし、確かによい行動だったとしても、「わざわざ指摘しなくてもいいのに」「指摘することで自分が不利になったり、危険な目に遭う可能性があるのに」と行き過ぎた行為だと感じる場面でもあるのではないでしょうか。
つまり、「正義感が強すぎる」という状態は、一律に善悪を判断できるものではなく、「強すぎる」という評価も、保護者や周囲の大人など特定の人の視点であることを意識することが大切です。
また、ある研究では、正義感を単一の概念としてではなく、複数の側面を持つ心理学的構成概念とする捉え方が提唱されており、単に「正義感が強い」と一括りにするのではなく、その内容が多様であることも示されています。
具体的には、正義感への感受性を下記の4つの側面に分けて考えることができます。
①不公正な出来事によって損失を受けることに対する感受性(他の人が自分よりも不当に恵まれている)

例)テストでカンニングをしている子を見つけた際に先生に言いつける
②不公正な出来事について第三者として知ることに対する感受性(誰かががその他の人よりも悪い状況に置かれている)

例)陰口を言われている子を見つけた際に放っておけずに援護する
③不公正な出来事から受動的に利益を得ることに対する感受性(他の人が得るべき利益を自分が受け取っている)

例)目立った成果を出した自分だけが先生に褒められ、協力してくれた他の友達は注目されていない時に罪悪感を感じる
④不公正な出来事を能動的に引き起こすことに対する感受性(自分が不正な利益を得ている)

例)グループワークで自分だけがあまり貢献できなかったにもかかわらず、他のクラスメイトの活躍のおかげで自分まで先生に褒められてしまった
このような前提を踏まえ、「正義感が強すぎる」と感じる場面に出会ったら、いきなり否定したり注意するのではなく、まずは子どものどんな行動が「行き過ぎている」と感じたのか、それはなぜか、を整理していくことが大切です。
正義感が強すぎるのはなぜ?発達障害との関係は?

ここでは正義感が強すぎる要因として考えられることや、発達障害との関係性について解説します。
生来的に持っているもの
研究によると、「弱者を助ける正義の行為」を肯定する傾向が発達の早期に認められています。つまり私たちヒトは、「正義」を肯定する心の特性(心的バイアス)を生来的に持っている可能性があるのです。
その本来持っている正義を肯定する心の特性が強く出やすい場合に、「正義感が強すぎる」と周囲にジャッジされてしまう可能性があります。
育った環境によるもの
家庭や園、学校のしつけや、教育方針によっては「正義感」を強くもつことが善とされる環境もあります。そうした環境で育った場合、正義感が強くなる場合があります。
例えば、クラスの先生が「弱い立場の人を助けられる、正義感が強い子はすばらしい」という思考を持ち、常にそういった行動をほめていた場合、そのクラスの生徒は学校集団の中でもより「正義感が強い」性質を持つ可能性が高くなります。
発達障害の特性が関係している
発達障害のある子どもの中には、「こだわりが強い」「感情や行動のコントロールが苦手」「相手の気持ちを汲み取ることが難しい」などの特性がある子どももいます。
こういった特性ゆえに、自分のルールを強要したり、相手の状況にかかわらず過度に注意するといった行動が目立ち、周囲には「正義感が強すぎる」という印象をもたらす可能性が考えられます。
子どもが正義感が強すぎる時の対処法

「正義感」は必ずしも悪いものではなく、困っている人を助けたり、リーダーシップを発揮できるなど、本人の長所となる可能性もあります。
しかし、正義感が強すぎることで、周囲とのトラブルが頻発していたり、本人が困りごとを抱えている場合には、次のような方法を試してみるのもよいでしょう。
いずれの方法も一度教えれば身につく、というものではなく、繰り返し伝える必要があります。また、何度練習したり、伝えてもなかなか状況が変わらない場合には、必要に応じて専門機関に相談しながら、原因や対処法を検討することが大切です。
ルールの例外や、なぜその場では許容されるのか背景を伝える
前述の通り、「正義感」というのはあくまで周囲からの評価であり、子ども自身は「正義」を前提に行動しているというよりも、親や先生に教わった「ルール」に従って行動しているケースが多々あります。
つまり、教わっているルールと現実に起きていることが競合している(が周囲はさまざま理由でそれを許容している)ときに、それを指摘する、ルール通りにすることを求める行動などを周囲が「正義感」という言葉で表現しているとも考えられます。
そのため、まずは、ルールや規則、校則には例外やグレーゾーンがあることを伝えることが大切です。
すべての例外を網羅することは難しいため、子どもの正義感が強すぎると感じる場面に応じて、その都度具体的に伝えていきましょう。
例えば、「校則では廊下は走ってはいけないと書いてあるけれど、緊急時にはその限りではない」「順番は守る必要があるけれど、さまざまな理由で守れない人もいる」などです。
国や文化、立場によって「正義」の在り方が違うことを教える
前述の「ルールの例外」以前の問題として、そもそもの「ルール」が違う場面も考えられます。
具体的には、国によって法律やマナーが違う、育った家庭によって家庭内のルールが違うことなどを伝えたうえで、自分の持つ「正義」や「正しさ」は自分が認知できる世界の範囲内で形成されたものであり、その外側にも別の「正義」がありうることを徐々に伝えていけるとよいでしょう。
口頭で説明するだけでなく、実際に異文化に触れる機会を作ることで、実感が湧き、より理解が深まることもあります。
相手の状況や気持ちを汲み取る練習をする
子どもの持っている特性によっては、相手の気持ちや状況を理解することが難しいこともあり、それゆえに良かれと思って行動した結果、周囲からは「正義感が強すぎる」と捉えられてしまうこともあります。
例えば、授業の練習問題が難しく、悩んでいるお友だちに対して「なんで早くやらないの?」「これくらい簡単だよ!」などと声掛けをしてしまうなどです。
子ども自身の成長や実際の体験を通して、相手の状況や気持ちを理解するスキルは自然に身についていくこともありますが、それが難しい場合は、ロールプレイングや具体的な場面の振り返りを通して、そのスキルを向上させることもできます。
行動や感情をコントロールする方法を身に着ける
子どもの特性によっては、行動や感情をコントロールすることが難しい場合や、コントロール方法を知らないということも考えられます。
そういった場合には、コントロール方法を教えたり、練習することが有効です。
例えば、不正やルール違反が気になって注意したいという気持ちが強くなったら 「発言の前に、5秒数える」など、子どもが実践しやすい方法で試してみましょう。
また、どうしても行動したいという欲求が抑えられない場合に備えて、対処法を考えておくことも大切です。前述の例だと「本人ではなく先生に言う」「連絡帳に書いておく」など「本人に注意する」以外の方法が取れるとよいでしょう。
相手を傷つけてしまった後の行動について話し合う
正義感が強すぎることで起きるトラブルとして、例えば、お友だちに強く注意をしてしまい結果的に相手が傷つくなどが考えられます。
もちろんトラブル事態を避けることも大切ですが、もし起きてしまった場合に備え、対処法を考えておくことも同じくらい大切です。
例えば上述の事例に挙げたトラブルが起きた際、「自分は正しいことを言ったまでだ」と開き直ってしまうと、より関係性が悪くなったり、その後の集団行動で子ども自身が生きづらくなる可能性もあります。
「謝る」「対話する」などができると理想的ではありますが、気持ちが高ぶっているとなかなか行動に移せないこともあります。本人と相談したうえで、「まずはその場を離れる」など現実的な行動を決めておき、落ち着ける場所で保護者や先生と一緒に振り返りの時間を持ったり、自分で紙に書きだすなどの方法が取れるとよいでしょう。
正義感が強すぎるお子さまへの指導事例

正義感の強さゆえ、トラブルが起きていた小学4年生のAくん
衝動性の強さと正義感の強さもあいまって、悪気なく、思ったことを相手にすぐに伝えてしまう傾向があったAさん。
ストレートな物言いのために相手が傷つき、トラブルになることも多くありました。その結果、学校の先生に怒られる経験も増え、悪気がないゆえに、悲しい思いをしていました。
支援の内容と成長の過程
アセスメントの結果、衝動性や正義感の強さの他に、相手の表情や様子の変化を読み取ることが難しいことや、伝えてしまった後の行動のレパートリーが少ないことがわかりました。
保護者との面談の結果、「衝動性の強さ」と「正義感の強さ」は長所としても活かせると判断し、授業では「相手の表情や状況を読み取るスキル」と「相手を傷つける行動をしてしまった後の対処法」の2つに集中してアプローチすることを決めました。
実際の授業では、「コミック会話」やロールプレイング動画を用いて、状況や相手の表情を説明することから始めました。
その後、その場面での望ましい行動を「選択肢から選ぶ」、「望ましい行動を自分で考える」と少しづつハードルを上げて練習を重ねました。実際に使ったのは下記の教材です。

支援のポイント
Aさんは「間違える」「指摘される」という状況になると、とてもネガティブな気持ちになる傾向があったため、はじめは正解しやすい選択肢を準備するなど、成功体験を積み重ねることができる環境づくりを心掛けました。
また、ロールプレイに関しても、決められたお題ではなく、Aさんが好きな折り紙などを題材に、実際に折り紙をしながら、指導員と自然なやり取りの練習をおこないました。
具体的には、事前に折り方や担当を決める話し合いの中で、あえて指導員が効率の悪い方法を提案したり、決めていた段取りをわざと間違えて失敗する場面を作りました。
Aさんは「違うってば!」「なんでできないの!!!」と強い言葉が出やすい傾向があったため、折り紙に取り組む前に、「先生、折り紙があまり得意じゃないから間違えてしまうかもしれない」「もし間違っていたり、違ったことをしていたら優しく教えてね」と伝えることで、「僕がここ手伝ってあげる」「ここはこうやってやるんだよ」と相手を気遣う声掛けが増え、良い行動でほめられる場面を増やすことを意識しました。
これにより、Aさんもモチベーションを保ちながら練習ができるだけでなく、より実際の場面に近い状況で相手の表情に目を向ける機会を作ることができました。
支援の成果
最終的には普段の生活の中で相手の表情に目を向けることができるようになり、学校でも少しずつトラブルが減っていきました。
家庭内でも、お父様に攻撃的な発言をしてしまったあとに、自分でクールダウンをし、「さっきはパパにきつく当たってしまってごめんなさい」などと自分の行動を振り返り、謝罪することができるようになりました。
まとめ
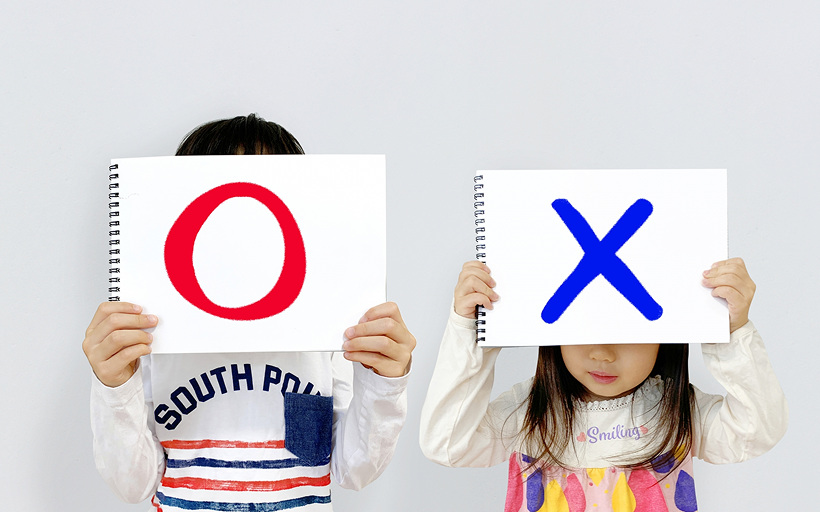
「正義感が強い」という言葉は、子どもの行動を評価する際によく使われ、背景には「扱いにくい」といったネガティブな意味も含まれることも多くあります。
しかし、この言葉は時に、子どもの内面や行動の真意を覆い隠してしまうことがあります。
子どもの「正義感」と見える行動は、単に「正しいことだから」という理由だけで行われているわけではありません。むしろ、子どもがこれまでに学んできたルールや規範と、実際に周囲で起きていることとの間に矛盾を感じ、それを指摘したり、ルール通りの行動を求めたりする結果として表れることが多いのです。
このような行動は、子どもが周囲の状況を敏感に察知し、論理的に物事を捉えようとしている証拠でもあります。
子どもの行動を「正義感」という一言で片付けるのではなく、その根底にある理由を理解することで、例えば「ルールへの意識が高い」「一貫性を大切にしている」「論理的思考ができる」など、違った角度で評価することもできます。
捉え方や言葉が変わることで、周囲も、その子ども自身もお互いが過ごしやすい環境を作っていくことができるのではないでしょうか。






