お役立ちコラム
子どもが計画を立てられない|要因や対処法、指導事例を紹介
2025.09.10公開
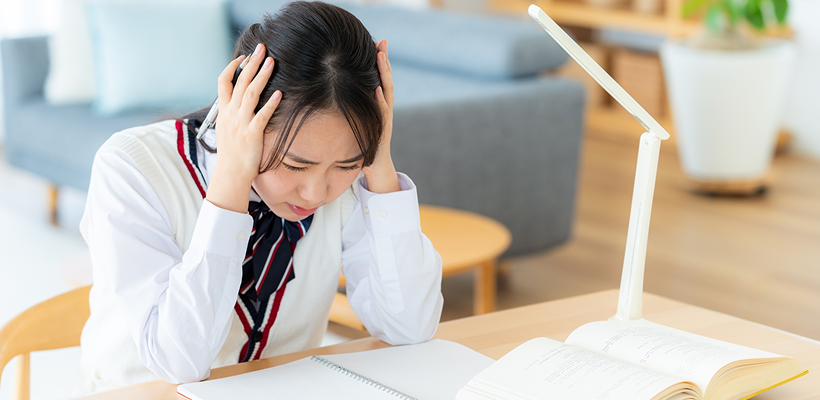
中学生や高校生の子どもが計画を立てるのが苦手だと、テスト勉強や将来の受験などでつまづいてしまうのでは、と悩んでいる保護者の方もいると思います。
計画を立てるのには多くのスキルを組み合わせて使うことが必要で、子どものうちに苦手なことは珍しくありません。ただ、現在困っている場合は何か対処することも必要かもしれません。
今回は要因として考えられることや対処法、計画を立てられない子どもへの指導事例を紹介します。
この記事を書いている会社:
株式会社LITALICO
LITALICOジュニアは、発達が気になるお子さま向けソーシャルスキル&学習教室です。
指導実績45,000人以上※1、 全国190教室以上※2、多くの指導実績を通して培ったノウハウに基づき、満足度の高いサービスを提供しています。
2024年8月時点(児童発達支援・放課後等デイサービス・パーソナル総数)
2024年9月時点(児童発達支援・放課後等デイサービス・パーソナル総数)
幅広いニーズと困りごとへの指導実績!
ADHD/自閉スペクトラム症/学習障害/グレーゾーン/言葉の遅れ/感情コントロールが苦手/コミュニケーションが苦手/学習の遅れ
計画が立てられない子どもに考えられる要因
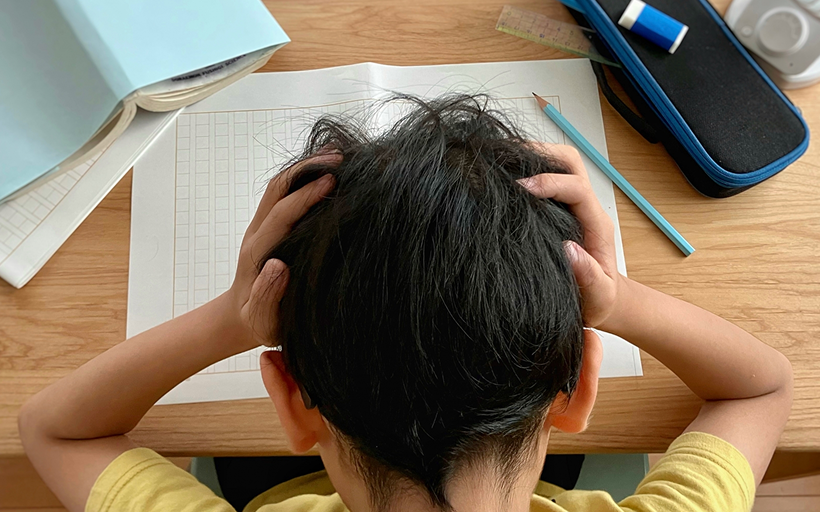
中学や高校に入ると子ども自身で計画を立てる機会が多くなります。計画が立てられないと定期テストや部活動、そして今後の受験勉強などに影響が出るかもしれないと不安な方もいるのではないでしょうか。
計画を立て、その通りに実行するにはさまざまなスキルが必要で、苦手であることは珍しくありません。しかし、ほかの子と比べても苦手な場合は何か要因があるかもしれません。要因は数多く考えられるため、紹介するものがすべてではありませんが代表的なものをいくつか挙げていきます。
優先順位がつけるのが苦手
物事に優先順位をつけるのが苦手だと、計画を立てようとしても「何から始めていいかわからない」ということになりがちです。また、優先順位以前にどういった作業や行動が必要かわからない、ということも要因として考えられます。
見通しを立てるのが苦手
必要な行動などはわかっても、先の見通しを立てるのが苦手だと計画を立てることもむずかしくなります。
例えば定期テストの勉強ではテスト日やテスト範囲から逆算して、「この日までにこの勉強をする」など計画を立てることが必要ですが、見通しを立てるのが苦手だとこの作業でつまづいてしまい、うまく計画が立てられないということが考えられます。
目の前のことに熱中してしまう
やることはわかっていても、目の前のことに熱中し過ぎてしまいスケジュール通りに進まなくなってしまうということも考えられます。またその逆で、注意が逸れやすく決めた作業に集中し続けるのが難しいという子どももいます。
その結果、計画を立ててもうまくいかなかったという経験を繰り返し、計画を立てること自体に苦手意識を持っているかもしれません。
計画を立てる能力は徐々に身についてくる
紹介してきた要因に思い当たることが多いと「うちの子はADHDなどの発達障害があるのでは?」と思うかもしれません。その可能性もあるかもしれませんが、計画を立てられないからといって発達障害とはいえません。
計画を立てるには遂行能力や実行能力といった、複雑なスキルが求められ、大人でも難しいものです。そのため、中学生や高校生の子どもが苦手でも不思議ではありません。
ただ、学校生活でつまづく要因となっていたり、思い悩んでいる様子があったりする場合は、次の章で挙げる対処法を一緒に試してみてもいいでしょう。
計画が立てられないときの対処方法

子どもが計画を立てるのが苦手で困っているときにできる対処法を、いくつか紹介します。全員に確実な方法はないため、子どもの特性や性格などに合わせて実行しやすい方法を探っていくといいでしょう。
また、そもそも子どもが完璧な計画を立てることは難しいため、サポートになればいいといった認識で取り組んでいくことが大事です。
やることを明確にする
「何から手を付けていいかわからない」という子どもには、やることを明確にすると計画を立てやすくなるかもしれません。例えば定期テストへの計画を立てる際には、テスト当日、期日、教科ごとのテスト範囲や勉強時間を明確にする方法があります。
また、頭の中だけで考えようとすると混乱することもあるので、紙に書きだして整理するとわかりやすくなる場合もあります。そのうえで、行動の優先順位もつけていきます。優先順位をつけるには練習が必要なので、最初は子どもの希望も聞きながらサポートしていくといいでしょう。
行動を細かく区切る
やることはわかっているけどうまく進めることが苦手、という子どもには行動を具体的に細かく区切る方法があります。単に「数学を勉強する」だけだとあいまいで具体的にどうしていいかわからなくなってしまうことがあります。そうすると、テスト当日までに必要な範囲が終わらなかったり、目の前の勉強に熱中し過ぎてほかの教科がおろそかになってしまうことも考えられます。
そこで、例えば数学をテストまでに100ページ勉強するとして、「何月何日は」「数学を」「教科書の1ページから10ページまで」「1時間勉強する」と区切ってやることを整理すると、一つ一つのことに集中しやすく、全体を通して計画通り進めやすくなります。
ページ数や時間設定は子どもの集中力に合わせて設定することが大事です。また、集中し過ぎてしまう場合はタイマーをセットするなど工夫しておくといいでしょう。
ツールを活用する
計画を立てるにはさまざまな能力が必要となります。それを頭の中だけで実行しようとしてもうまくいかないことも多いと思います。そこで、計画作成の助けとなるツールを活用していく方法を紹介します。
代表的なツールとして、以下があります。
- TODOリストやスケジュール帳
- スマホのアラームや通知機能
- スマホの計画作成アプリ
例えば、TODOリストに定期テストまでに必要な勉強を優先順位順に書いておき、達成できたらチェックをつける方法があります。見開きのスケジュール帳にテスト日やそれまでに必要な作業を書いておくと、視覚的にイメージしやすくなるという場合もあるでしょう。また、こういったツールは常に目に見える場所(机の上の所定の位置、冷蔵庫に貼るなど)にあると、そもそも見るのを忘れていた、という事態を防げます。
勉強の計画を立てるアプリもたくさんあります。勉強時間を記録できたり、絵柄がかわいかったりと機能もそれぞれ違っているので、子どもの特性に合ったアプリを選ぶといいでしょう。
また、デジタルは合わずアナログの手帳やTODOリストに書いた方が実感しやすいという子どももいます。いろいろと試してみて、マッチするものを探していくといいと思います。
計画が立てられない子どもへの指導事例

計画を立てるサポートは、家庭だけでなく放課後等デイサービスなどでも受けることができます。ここでは、実際に行われた計画を立てるための指導を紹介します。
Aさんの事例
Aさんは高校3年生になって大学選びや受験勉強が必要になったときに、「自分で計画を立てることができない」という悩みに直面しLITALICOジュニアに相談に行きました。
LITALICOジュニアではまずAさんがどこでつまづいているのかを把握することに。その結果「自分の得意不得意がわからない」「優先順位をつけるのが苦手」という傾向がわかってきました。
この傾向をもとに指導員が指導計画を立て、まずは得意不得意の把握から開始することになりました。Aさんは視覚優位だったため、その特性を活かしてリフレーミングカードを用いて得意なことを、困り度マップを用いて不得意を洗い出してきました。
そして、把握した得意なことから進路先の分野を絞り、不得意なことも踏まえて選択した学校への入学が現実的か優先順位をつける練習も実施。
その結果、Aさんは自分に合った大学を選択することができ、受験勉強でも優先順位をつけて勉強し見事合格。「大学の履修登録も本人だけでできた」と保護者から喜びの声をいただきました。
使用した教材
今回の指導で使用したのはリフレーミングカードと困り度マップです。
リフレーミングカードは同じことをポジティブな面とネガティブな面で言い表したカードで、本人が得意と感じていることを洗い出すことに使用しました。

困り度マップは「部屋を片付ける」「予定通り行動する」などの場面が書かれたカードを、程度などによって区切ったマップに配置することで、本人の苦手なことやその度合いを明確にしていく教材です。

LITALICOジュニアの指導
計画が立てられないという困りごとがあっても、その要因や解消方法は一人ひとり違っています。そのため、LITALICOジュニアでは子どもの様子を見たうえで教材を用意し、それぞれにマッチした指導を実施しています。
LITALICOジュニアでは、通所受給者証をお持ちの方が利用できる「児童発達支援」「放課後等デイサービス」と、どなたでも利用できる「幼児教室」「学習塾」があります。詳しいことを知りたい方はご相談いただければと思います。
まとめ

中学生や高校生の子どもが計画を立てられないと、学校生活や将来の受験、仕事などに影響があるのではと不安な方もいると思います。
計画が立てられないのにはさまざまな要因が考えられ、それによって対処方法も変わってきます。ただ、子どものうちは計画が立てられないのは珍しいことではないので、あまり完璧は求め過ぎずに少しずつできるようにサポートしていくことが大事です。
LITALICOジュニアでも計画を立てるためのサポートを行っています。子ども一人ひとりの性格や特性をよく見て要因を探り、その子に合った指導を心がけているので、「計画が立てられなくて心配」という方は、ぜひ一度お問い合わせください。






