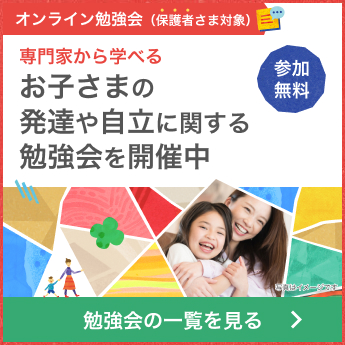療育手帳は、知的障害(知的発達症)のある方が申請できる手帳で、地域によっては愛の手帳などとも呼ばれています。
療育手帳を取得することで、交通機関の割引や税金の控除を受けることができるなどさまざまなメリットがあります。
とはいえ、「子どもが手帳の対象かどうかわからない」、「発達障害の子どもも申請できるの?」、「メリット以外にデメリットもある?」など、疑問をお持ちの方や取得すべきかどうか悩まれている方も多いと思います。
この記事では、子どもの療育手帳について、対象となる障害、取得した場合のメリット・デメリット、申請方法などをくわしくご紹介します。
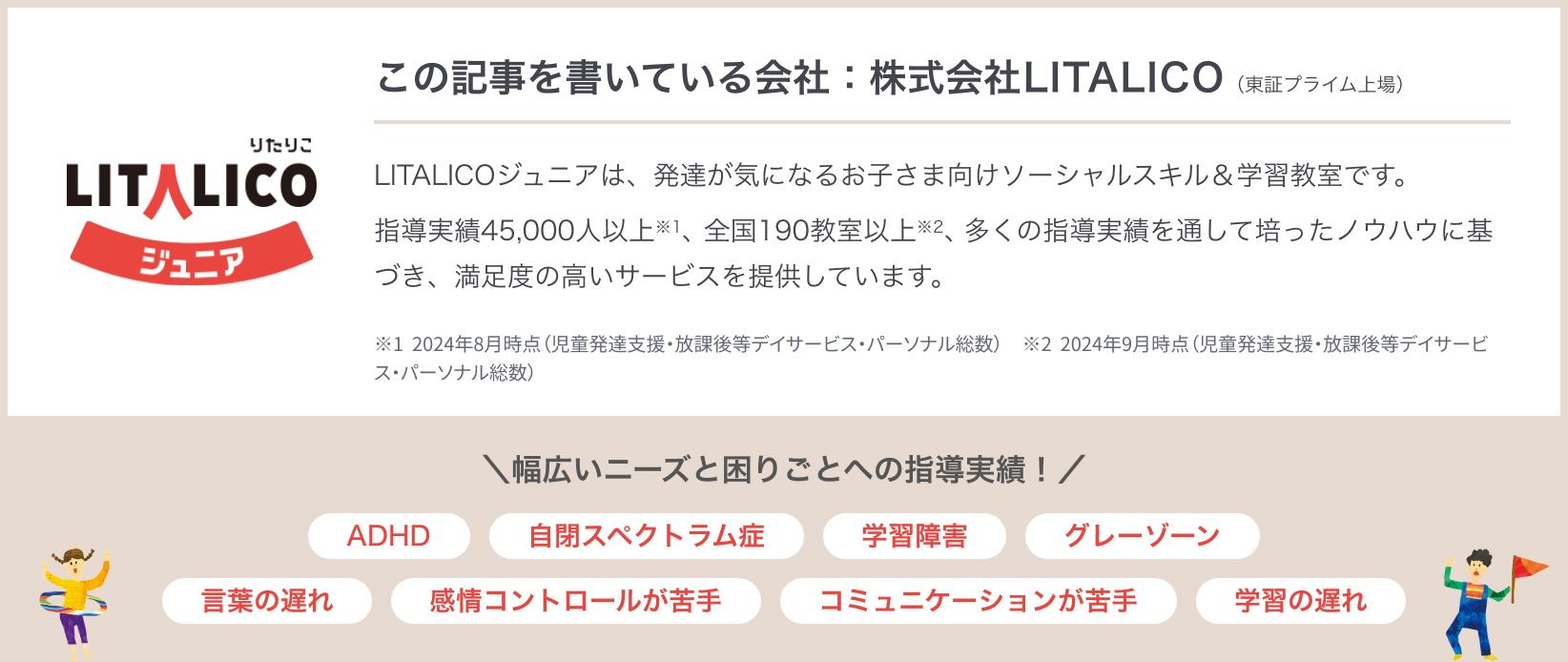
療育手帳(愛の手帳)とは?他の障害者手帳との違い
療育手帳とは、知的障害のある方に交付される手帳で、さまざまなサービスや支援を受けることができるメリットがあります。
まず、障害のある方を対象とした手帳として「障害者手帳」があり、療育手帳もそのうちの一つです。
障害者手帳には3種類あり、
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳
- 療育手帳
となっています。
障害者手帳は種類ごとに対象となる障害が異なっているほか、運用方法にも違いがあります。身体障害者手帳と精神障害者保健福祉手帳は法令に基づいて運用されていますが、療育手帳は厚生労働省の方針のもと都道府県などの自治体が独自に運営をしています。
そのため、療育手帳は各自治体で名称や受けることができるサービスが一部違っているという特徴があります。
例えば東京都では療育手帳は「愛の手帳」と呼ばれています。ほかにも例を記載します。
- 愛の手帳…東京都、横浜市
- 愛護手帳…名古屋市、青森県 など
療育手帳の主な記載内容は、以下のとおりです。
- 知的障害者の氏名、住所、生年月日及び性別
- 障害の程度(重度とその他の別)
- 保護者(親権を行う者、配偶者、後見人その他の者で知的障害者を現に監護する者)の氏名、住所及び知的障害者との続柄
- 指導、相談等の記録
療育手帳の対象は?
療育手帳は知的障害のある方が対象となります。より具体的にいうと、児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害(知的発達症)であると判定された方が対象です。
療育手帳の交付対象になるかどうかは、18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で判定を受ける必要があります。
何歳以上でないと取得できないといった決まりはないですが、新生児や乳児だと知的障害(知的発達症)だと診断することがまだ難しく、療育手帳の交付が難しいという場合もあるようです。
発達障害のある方も対象?
発達障害のある方は療育手帳ではなく、精神障害者保健福祉手帳が対象となります。
しかし、発達障害に知的障害が伴っている場合には療育手帳を申請することも可能です。療育手帳における知的障害のあるなしは子どもの場合は児童相談所で判定することになります。子どもに発達障害があって、障害者手帳の取得について迷っている方は児童相談所や自治体の障害福祉窓口などに相談してみるといいでしょう。
療育手帳の等級と判定基準
療育手帳は障害の程度によって、等級が分かれます。等級によって、受けられるサービスの内容や程度が変わるため、以下では、等級の区分やその判定の基準についてご紹介します。
療育手帳の等級
療育手帳の等級は厚生労働省が出している指針においては「重度」と「その他」の2つに分かれています。また、それ以外にも自治体独自にa判定、b判定などの判定基準を設けている場合があります。
例えば横浜市では等級は、
- A1(最重度)
- A2(重度)
- B1(中度)
- B2(軽度)
の4つに分かれています。
ほかにも、各自治体における療育手帳の等級区分をいくつかご紹介します。
- 東京都:1度(最重度)、2度(重度)、3度(中度)、4度(軽度)
- 埼玉県:Ⓐ(最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)
- 青森県:A(重度)、B(重度以外)
- 大阪府:A(重度)、B1(中度)、B2(軽度)
療育手帳の判定基準
厚生労働省によると、療育手帳の判定基準は、主に重度(A)とそれ以外(B)に区分されています。
重度(A)の判定基準
厚生労働省の指針を基に重度(A)の場合の判定基準を紹介します。
- 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
異食、興奮などの問題行動を有する。 - 知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
それ以外(B)の判定基準
重度(A)判定以外の判定基準は厚生労働省では重度のもの以外となっているため、自治体独自に制定していることが多くなっています。ここでは、兵庫県のB判定の例を紹介します。
兵庫県ではB判定は中度B(1)と軽度B(2)に分かれているので、それぞれ基準を記載します。
- 中度B(1):新しい状況や自体の変化に適応する能力が低く、ほかの人の助けがあって自分の身辺のことがこなせる方
- 軽度B(2):日常生活にさしつかえない程度に自分の身辺のことをこなせるが、抽象的な思考や推論などが難しい方
療育手帳を取得するメリット

療育手帳を取得することでさまざまなサービスや控除を受けることができるメリットがあります。
療育手帳の等級やお住まいの自治体によって受けられるサービスが異なるので、詳細はお住まいの自治体の窓口にお問い合わせください。
以下では療育手帳を取得することで受けられるサービスを一部ご紹介します。
障害児福祉手当など手当の給付
障害のある子どもやその保護者が受給できる手当があります。受給するには、条件を満たし申請する必要があります。
障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害があることで、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者が対象となります。
支給額(月額):15,220円
所得制限あり
特別児童扶養手当
20歳未満の障害児を養育する保護者が対象となります。障害の程度に応じて1級または2級として認定されます。
支給額(月額):1級53,700円/2級35,760円
所得制限あり
税金の控除や減免
療育手帳を交付されている方は、税金の控除を受けることができるメリットもあります。具体的には、以下のような税金が控除されます。
所得税
本人、同一生計の配偶者または扶養親族に障害がある場合、控除を受けることができます。
障害者(療育手帳の等級がB相当):27万円
特別障害者(療育手帳の等級がA相当):40万円
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族:75万
住民税
本人、同一生計の配偶者または扶養親族に障害がある場合、控除を受けることができます。
障害者(療育手帳の等級がB相当):26万円
特別障害者(療育手帳の等級がA相当):30万円
特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族:53万
自動車税・軽自動車税
療育手帳の交付を受けている本人が運転する場合、または、本人と生計をともにする方が、障害のある方の通院や通学・通勤などのために運転をする場合は、申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができます。
公営住宅の優先入居
療育手帳を所持していると、公営住宅に優先入居できるというメリットもあります。具体的な内容は自治体によって違いがありますが、ここでは横浜市の例を紹介します。
横浜市では
A1~B1の愛の手帳(療育手帳)の交付を受けている方を対象として、
- 一般申込者より当選率を優遇
- 入居収入基準の世帯の月収額の緩和
- 宅使用料の特別減額制度が適用される場合がある(所得制限あり)
といった制度を実施しています。
詳しいことはお住いの自治体の障害福祉窓口などでご確認ください。
公共料金などの割引
療育手帳を所持していることで、NHKの受信料など公共料金の割引を受けることができるメリットもあります。具体的には以下のような公共料金が割引もしくは無料になります。
NHK放送受信料の減免
全額または半額免除されます。免除の割合は障害程度によって異なります。
携帯電話料金の割引
携帯電話の基本使用料などの割引を受けることができます。割引の範囲や割引率は、携帯会社ごとに異なります。
公共施設の無料入場など
療育手帳を提示すると、入園料や利用料が無料となる施設があります。例えば、美術館・博物館・動物園、映画館などが対象になることがあります。
交通機関の割引
療育手帳を提示することで、JRなどの交通機関の料金が割引、無料になるというメリットもあります。具体的には以下のようになっています。
JRなど運賃の割引
療育手帳を提示することで、本人とその介護者の運賃が5割引になります。民間会社が経営する鉄道でも割引になりますが、割引率や取扱いが異なる場合があります。
航空運賃の割引
運賃の割引率は、航空会社によって異なります。搭乗時の年齢が満12歳以上で療育手帳を持っている者、および、同一便に搭乗する満12歳以上の介護者(一人まで)が利用できます。
民営バスの割引
療育手帳を提示することで、本人とその介護者の運賃が割引されます。各バス会社で割引率や取扱いが異なります。
児童発達支援・放課後等デイサービスの利用
療育手帳を持っていることが条件ではありませんが、療育手帳を持っていると、子どもが支援を受けやすくなることがあります。
例えば、子どもが必要なスキル獲得のためのトレーニングが受けられる児童発達支援・放課後等デイサービスの利用申請がスムーズになることがあります。
手続きの流れや必要な書類は自治体ごとで異なるので、お住まいの市区町村の福祉担当窓口でご確認ください。
LITALICOジュニアでも、児童発達支援事業所、放課後等デイサービスを各地に展開しており、一人ひとりに合わせた支援を行なっています。気になる方はお気軽にお問い合わせください
療育手帳を取得するデメリット
療育手帳を取得したことでデメリットになることは基本的にはないと言えるでしょう。自分から言い出さない限り、療育手帳を所持していることが周りの人に伝わることもありません。
人によってデメリットと感じるかもしれないことに、紛失や引っ越しをした場合に再取得や住所変更などの手続きが必要なことがあります。また、数年に一度更新の手続きが必要になることもあります。こういった管理面での手間をデメリットととらえる方もいるでしょう。
しかし、療育手帳は知的障害(知的発達症)があるからといって、必ず取得しなければいけないというわけではありません。また、療育手帳を持っている必要がなくなったら返納することもできます。
そのため、療育手帳を取得するかどうかは、受けたい支援やサービスがあるかなど、それぞれの状況に合わせて検討するのが良いでしょう。
療育手帳の申請方法

実際に申請する場合の主に必要とされる書類や申請の流れについてご紹介します。
詳細は各自治体によって異なりますので、申請される際にはお住まいの障害福祉窓口にお問い合わせください。
療育手帳の申請に必要な書類等
申請する際にはいくつか必要な持ち物があります。各自治体で必要な書類が異なりますが、ここでは主に必要とされる持ち物をご紹介します。
- 手帳交付申請書:自治体の福祉担当窓口でもらうことができます。
- 写真:サイズなど規定が決まっている場合があります。
- 印鑑
- マイナンバーカード
- その他添付書類
医師による診断書や意見書などが必要な自治体もあります。
療育手帳の申請の流れ
申請は以下のような流れで行われます。
- 窓口に申請
- 判定
- 交付
窓口に申請
申請はお住まいの自治体の障害福祉窓口が担当しており、本人または保護者が申請をします。
判定
判定は、18歳未満の場合は児童相談所、18歳以上の場合は知的障害者更生相談所で受ける必要があります。療育手帳を取得する際の具体的な判定内容は、各自治体や年齢ごとで変わります。
一例として東京都の判定項目をご紹介します。
- 心理判定員から本人、保護者へのヒアリング
生育歴や日常生活について、18歳までの知的発達の状態と本人の現在の状況など - 知能検査の実施
- 身長・体重の計測
- 精神科医師から本人や保護者へのヒアリング
精神的・身体的合併症や問題行動についてなど - 精神科医師による知的障害(知的発達症)かどうかの診断
これらの結果から、精神科医、心理判定員などの協議により総合判定が行われます。
交付
判定の結果、該当すると認められた場合、通常2ヶ月~2ヶ月半ほどで手帳が交付されます。
療育手帳の更新
療育手帳は数年に一度更新の手続きを行う必要があります。
更新の頻度は自治体によって異なりますが、東京都の場合は、3歳・6歳・12歳・18歳で再判定を受ける必要があります。ほかの自治体では、年齢ごとに2年や5年という期間で更新を必要とする場合もあります。
また、障害の程度が変化したと思われた際には、該当年齢やタイミングでなくても再判定を受けることができます。
障害のある子どもの相談先
療育手帳を所持していなくても、子どもの発達が気になる場合に相談できる身近な窓口があります。また、療育手帳を申請するか迷っている場合にも相談することができ、取得することのメリットなども教えてもらうことが可能です。
主な相談先として
- 児童相談所
- 児童家庭支援センター(子ども家庭支援センター)
- 保健センター
- 自治体の子育て窓口
- 児童発達支援センター
などがあります。
相談は対面だけでなく電話などで行うことができる場所もあります。
子どもの状態などを含めて相談しやすい窓口に問い合わせてみるといいでしょう。
療育手帳のまとめ
知的障害(知的発達症)のある子どもやその保護者にとって、療育手帳によるメリットは大きいといえるでしょう。早期に療育手帳を取得することで、はやくから適切な支援やサポートを受けることができます。
療育手帳の取得を検討してみようかなと思ったら、お住いの障害福祉窓口に相談に行ってみてください。
LITALICOジュニアでは、療育手帳の対象となる子どもの支援を行っています。
障害のある子どもへの支援の場として、各地で児童発達支援事業所、放課後等デイサービス、幼児教室・学習塾を展開し、一人ひとりのニーズや特性に合わせて学習やソーシャルスキルアップをメインとした授業で子どもの成長をサポートをしています。
LITALICOジュニアでは知的障害(知的発達症)のある子どもの指導実績も多くありますので、子どもの発達についてのお悩みがありましたら、お気軽にLITALICOジュニアにご相談ください。