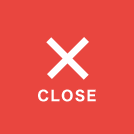広汎性発達障害(ASD/自閉スペクトラム症)とは
広汎性発達障害(ASD/自閉スペクトラム症)の症状
以前は対人関係の困難、パターン化した行動や強いこだわりの症状がみられる障害の総称として「広汎性発達障害」が用いられていましたが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)では自閉的特徴を持つ疾患は包括され、2022年発刊の『DSM-5-TR』では「ASD(自閉スペクトラム症)」という診断名になりました。
本記事では、DSM-5-TRの診断名であるASD(自閉スペクトラム症)を併記します。
ASD(自閉スペクトラム症)については、 こちらの記事をご覧ください。
最近は、発達が気になるお子さまへの早期療育をおこなう例が増えてきています。早期から介入し療育をおこなうことで、特性自体を治療することは難しいものの、いじめ、不登校、抑うつなど二次的な問題を予防することがきると言われています。
広汎性発達障害(ASD/自閉スペクトラム症)のあるお子さまによく見られる行動
幼児期(0歳~小学校就学)
広汎性発達障害(ASD/自閉スペクトラム症)は発達障害のひとつですが、発達障害は、言語・認知・学習といった発達領域が未発達の乳幼児では、その特徴となる症状が分かりにくい場合がほとんどです。ですから、生後すぐに広汎性発達障害(ASD/自閉スペクトラム症)の診断がでることはありません。
しかし、幼児期全体を通してみると、以下のような特徴的な行動をとっていたことが多いと言われています。
-
周囲にあまり興味を持たない傾向がある
視線を合わせようとしない、他の子どもに興味をもたない、名前を呼んでも振り返らない、といった状態が見られることが多いといわれています。定型発達の場合、興味をあるものを指でさして周囲の人に伝えようとするのに対し、広汎性発達障害(ASD/自閉スペクトラム症)であると指さしをして興味を伝えることをしない傾向があります。
-
コミュニケーションを取るのが苦手
知的障害(知的発達症)を伴う場合、言葉の遅れや、オウム返しなどの特徴がみられることが多いといわれています。会話においては、一方的に言いたいことだけを言う、質問に対してうまく答えられない、などの特徴が見られることがあります。同世代の定型発達の子どもがごっこ遊びを好むのに対し、広汎性発達障害(ASD/自閉スペクトラム症)の場合は集団での遊びにあまり興味を示さない傾向にあります。
-
強いこだわりを持つ
興味を持つことに対して、同じ質問を何度もすることが多い傾向にあります。また、日常生活においてもさまざまなこだわりを持つことが多いので、ものごとの手順が変わると混乱してしまうこともあるでしょう。
児童期(小学校就学~卒業)
児童期には、主に小学校での集団生活や学習において、以下のような特徴が現れやすくなります。
-
集団になじむのが難しい
年齢相応の友人関係を築くのが難しいお子さんも多くいます。自分が好きなように振る舞ったり、好きなことだけに取り組んだりするといった場面もみられます。人と関わるときは、何かしてほしいことがある場合が多く、基本1人遊びを好む傾向にあります。相手の気持ちや意図を汲み取ることを苦手とする子も多いでしょう。
-
臨機応変に対応するのが苦手
きちんと決められたルールを好む場合が多く、言われたことを場面に応じて対応させることが苦手な傾向にあります。
-
「どのように」「なぜ」といった説明が苦手
言葉をうまく扱えず、意味を理解することが難しい場合もあります。また、自分の気持ちや他人の気持ちを言葉にしたり、想像したりするのも苦手です。そのため、説明ができないこともあります。
思春期(小学校卒業~)
中学生以降の思春期では、以下の様な特徴が現れやすくなります。
-
不自然な喋り方をする
抑揚がない、不自然な話し方をする子が多い傾向にあります。
-
人の気持ちや感情を読み取るのが苦手
コミュニケーションが不得手で、相手が何を考えているのかなどを想像することについても苦手な傾向にあります。
-
雑談が苦手
目的の無い会話をするのを難しく感じる子が多い傾向にあります。
-
興味のあるものにはとことん没頭する
広汎性発達障害の特性に、物事に強いこだわりがあります。そのため、興味のあることにとことん没頭することが多く、その分野で大きな成果をあげられることもあります。
※上記にあげた例は行動の一例です。必ずしもすべてのお子さまに該当するとは限りません。
LITALICOジュニアでは、お子さまの感覚や行動の特徴、獲得スキルなどを専門のスタッフが分析するアセスメントを実施しています。感覚の特徴を知ることで、お子さまへの接し方や環境調整の仕方が分かるため、スムーズに生活するためのサポートがしやすくなります。
広汎性発達障害(ASD/自閉スペクトラム症)のあるお子さまとの接し方
広汎性発達障害(ASD/自閉スペクトラム症)のあるお子さまと関わるときには、以下のような工夫があることで生きづらさをやわらげることにつながります。
-
1声かけは短く、具体的に、ゆっくりと
遠回しな表現や代名詞や、「ちゃんと」などの抽象的な表現を使うと混乱する可能性があるため、「○○をします」など具体的に声掛けをしましょう。
-
2取り組みやすい環境を準備
広汎性発達障害(ASD/自閉スペクトラム症)のお子さまは、聴覚や触覚などの感覚が過敏な場合があります。その場合、周囲の刺激が気になって活動に取り組みにくくなります。そのため、掲示物など、ものが少なく静かな環境を整える工夫をしましょう。
また、空間を目的ごとに区切って何をするのか明確に示すのも取り組みやすい環境の工夫の1つです。さらに、音声よりもイラストや写真で活動の手順が分かることや、活動の区切りが明確であることもお子さまによっては安心に繋がる1つの工夫と言えるでしょう。 -
3興味関心を広げる関わりを
興味関心を広げるために、そのお子さまが熱中しているものを取り上げるのではなく、「○○もやってみよう」と見本を見せるなどして誘ってみるとよいでしょう。もちろん無理強いはせずに、少しずつ取り組んでいくことがポイントです。
-
4興味関心をいかした学びを
興味関心が限定的なお子さまには、その興味関心を取り入れることも1つです。例えばゲームが好きなお子さまにはプリント1枚ごとに1ポイント!とゲーム形式にしてみることでお子さまが取り組みやすくなります。
-
5パニックには冷静に
お子さまがパニックになったときには、指示を出しても声をかけても落ち着くのは難しいです。静かで刺激のない場所に連れていくなど安全を確保した上で、冷静に関わるようにしましょう。
※上記は接し方の一例です。必ずしもすべてのお子さまに該当するとは限りません。
※以前は対人関係の困難、パターン化した行動や強いこだわりの症状がみられる障害の総称として「広汎性発達障害」が用いられていましたが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)では自閉的特徴を持つ疾患は包括され、2022年発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。
LITALICOジュニアで実施する心理検査では、全体的な発達水準を把握し、お子さまの得意・不得意などの発達のバランスを客観的に見ることができます。
【参考資料】
- 広汎性発達障害とは?(LITALICO仕事ナビ)
https://snabi.jp/article/77#dlg20 - 広汎性発達障害(PDD)とは?年齢別に症状の特徴を解説!(LITALICO発達ナビ)
https://h-navi.jp/column/article/175 - 広汎性発達障害(PDD)とは?(発達ナビ)
https://h-navi.jp/column/article/175
*書籍
『イラスト図解 発達障害の子どもの心と行動がわかる本』田中康雄/監修、西東社/刊
文責:小更由
監修者:博士(障害科学) 野口晃菜