
ヘルプマークは、街中や電車などさまざまな場面で「配慮や援助が必要であることをまわりの方々へ伝えるためのマーク」です。
ヘルプマークを身につけると、あらかじめ周囲になんらかの障害や疾患のあることを表すことができたり、周囲から手助けしてもらいやすくなるため本人の安心感にも繋がります。
しかし「ヘルプマークという名前は聞いたことがあるけれど、詳しくは知らない」「どんなことを書いたらいいのかわからない」「活用方法は?」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、ヘルプマークの対象者や対象となる病気や障害、もらい方や使い方についてわかりやすく解説していきます。
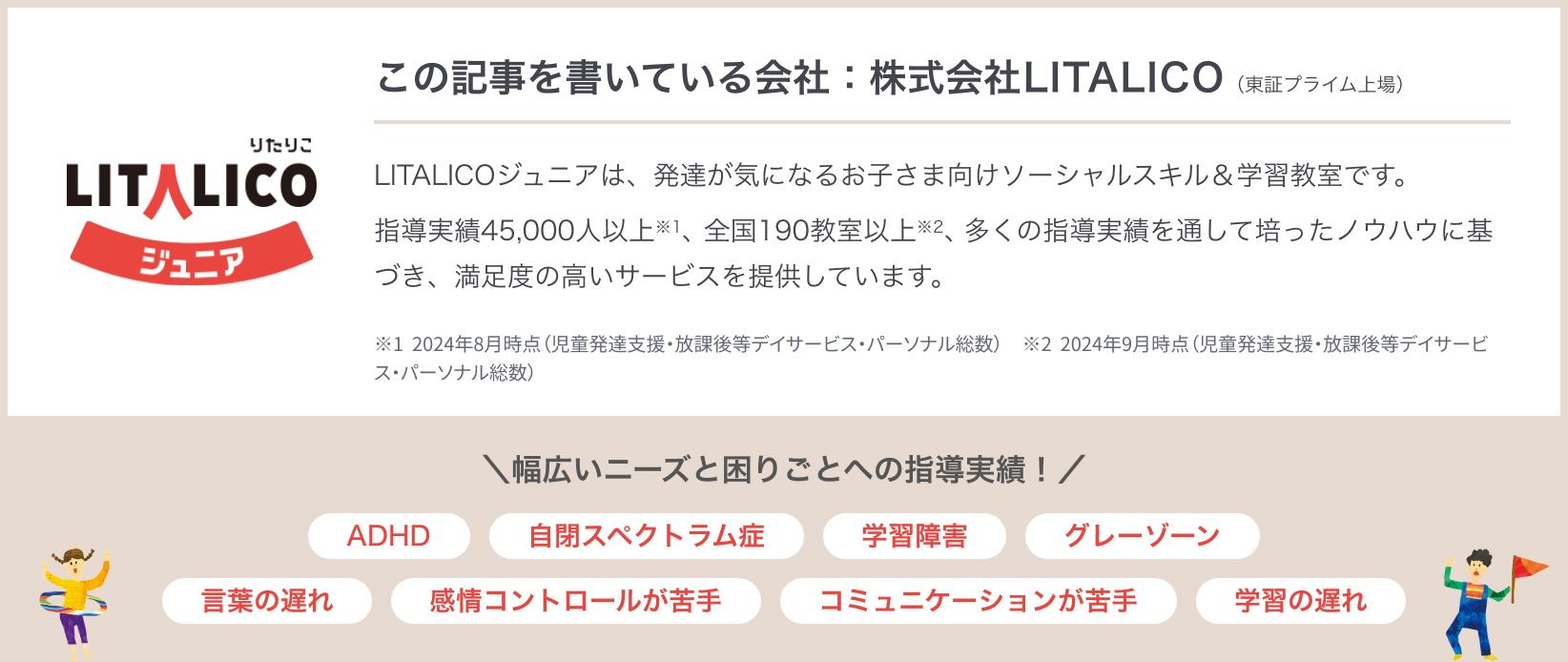
ヘルプマークとは
ヘルプマークとは、外見からはわかりにくい事情のある方が「周囲の方の援助や配慮を必要としていること」を知らせ、サポートを得やすくするために作成されたマークのことです。

ヘルプマークは令和3年3月時点で全国47都道府県に普及していて、東京都だけで約46万5千個を配布していると発表されています。
ヘルプマークのデザイン自体は全国共通で、キーホルダーのようにカバンなどにつけることができるようになっています。
また、ヘルプマークの裏面には、名前や連絡先、必要としている援助などを書き込めるシールを貼ることができます。
ヘルプマークをどのように使用するかというと、例えば急に大きな音が聞こえるときにパニックになることがある方が、ヘルプマークに「感覚過敏があるので困っているときは静かな場所に移動させてください」と記載しておくといった使い方があります。
また、心臓の疾患など見た目ではわかりづらい難病がある方も、ヘルプマークをつけておくことで、電車などで席を譲ってもらえることが多くなるという場合もあるようです。
ヘルプマークは裏面に障害名や配慮してほしいことなどを記載したシールを貼ることができます。
具体的な項目としては
- 名前
- 緊急連絡先
- 必要な支援や援助(例:耳が聞こえないため筆談をお願いします など)
といったことがあります。
シールはヘルプマークに同封されているため、すぐに記入して使えますが他の人が見る可能性もありますので、個人情報をどこまで記載するか、よく検討した上で利用しましょう。
具体的なヘルプマークの記入例は後ほど紹介します。
発達障害も対象となる?
ヘルプマークは援助や配慮の必要性が外見からはわかりづらい方向けのマークで、特に対象となる疾患などの基準が設けられているわけではありません。
外見からは見えない困難を示すためのものなので、発達障害や精神障害などのある方も必要に応じて入手することができます。
ヘルプマークの対象者

ヘルプマークの対象者は、主に外見からはわかりづらくても何らかの援助を必要としている方となっており、具体的には次に挙げるような方々です。
ヘルプマークの対象となる障害や病気一覧
東京都福祉保健局のWEBサイトには、下記にあてはまる方がヘルプマークの対象になると記載されています。
-
義足や人工関節を使用している方
-
内部障害のある方
-
難病のある方
-
妊娠初期の方 など
特にヘルプマークの対象となる病気の一覧があるわけではなく、外見からはわかりづらい困難がある方が対象となるようです。
実際に、精神障害や発達障害のある方、感覚過敏によりマスクの装着が難しい方、認知症の方など、配慮や援助が必要な幅広い方がヘルプマークを活用しています。
ヘルプマークは条件に該当すれば、医師の診断書や障害者手帳を持っていない方も申し込むことが可能ですが、「自分の症状でもらっていいのだろうか?」と悩む場合は自治体の障害福祉窓口などに相談してみるといいでしょう。
ヘルプマークのもらい方は?

ヘルプマークは、各地の市役所や区役所など指定の窓口で入手することが可能です。診断書や障害者手帳などは必要なく、申請をすることでもらうことができます。本人または代理人(ご家族や支援者)が窓口へ申し出をすることで、一人につき1枚配布してもらうことが可能で、自治体によっては、「ヘルプマーク交付申請書」の記入を求められることもあります。
ヘルプマークはどこでもらえる?
ヘルプマークをもらえる場所は自治体によっても若干異なりますが、一般的には市役所や区役所の福祉課などの窓口です。また、保健センターなどの場所で配布している自治体もあります。
主な配布場所
- 保健センター
- 障害者支援センター
- 市民センター
- 一部の病院 など
配布場所は自治体によって異なりますので、詳しくはお住まいの自治体のホームページなどでご確認ください。
駅でもらえることもある
ヘルプマークは自治体によっては駅でもらえる場合もあります。東京都では都営地下鉄の駅で配布しているほか、都営バスの営業所でももらうことができるようです。ほかにも民間の鉄道会社の駅でも配布している場合があります。
ただし、すべての駅で配布しているわけではないため、もらう前にあらかじめ確認しておくようにしましょう。
ヘルプマークを直接もらえない場合は?
ヘルプマークをもらえる窓口を紹介してきましたが、何らかの事情で直接もらえない場合の方法も紹介します。
ヘルプマークは郵送でもらうことも可能です。郵送方法はお住いの自治体のホームページなどで確認することができます。
なお、ヘルプマーク自体は無料ですが、郵送でもらう場合には郵送料がかかりますのでご注意ください。
ヘルプマークは自作もできる
なにかしらの事情によりヘルプマークをもらいに行けなかったり、自治体が郵送に対応していなかったりする場合は、ヘルプマークを自作することが可能です。
東京都福祉保健局などのWEBサイト上から「ヘルプマーク画像」をダウンロードし、紙に印刷して使いましょう。
印刷したヘルプマークは、大きさの変更は可能ですが、縦横の比率や色の変更は禁止となっています。そのほかの注意事項も確認したうえでお使いください。
ヘルプマークの種類とは?
ヘルプマークの基本的なデザインは統一されていますが、素材やサイズなどは決まっておらず、自治体によってさまざまな種類があります。また、ヘルプマークと一緒にさらに詳細な情報が書けるヘルプカードが配布される場合もあります。
また、ヘルプマークと同様に日常生活で何か困難があることを伝えるマークがいくつかあります。
ここでは以下の3つを紹介します。
- 耳マーク
- ハート・プラス マーク
- 聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)
耳マークは聴覚障害など耳が聞こえない・聞こえづらいことを示すマークです。また、役所の窓口などに掲示されている場合は、筆談などの聞こえに対して配慮した対応が可能なことを表しています。

ハート・プラス マークは身体内部に障害のあることを示しているマークです。
身体内部の障害とは、心臓や呼吸機能、膀胱・直腸、免疫機能などの障害のことを指しており、電車などの席や駐車場での配慮などが必要になることがあります。

聴覚障害者標識(聴覚障害者マーク)とは、聴覚障害のある方が車を運転するときに付けることが義務付けられているマークです。
このマークを付けた車に割り込みなどを行った運転者は、やむを得ない場合を除き道路交通法違反となります。

ヘルプマークとヘルプカードとの違い
ヘルプマークについて調べていると「ヘルプカード」という言葉を見かけるかもしれません。
ヘルプカードは、自治体によって様式が異なりますが、基本的にはヘルプマークよりもさらに詳しい情報が記入できるカード仕様になっています。
具体的な記入項目は多岐にわたりますが、
- 緊急連絡先
- 障害・病気の名前と特徴
- 血液型
- かかりつけ医
- 薬について
- 支援が必要な項目
- アレルギー
- 自由記述
- この手帳を自分が記入した日
- 障害に関するシンボルマーク など
を記入することが多いようです。
ヘルプカードは自治体ごとに様式が異なり、東京都では丈夫な素材で免許証程度の大きさ、色は白、ヘルプマークと「あなたの支援が必要です。」の文言を印刷することなどが定められています。財布などに入れておくことや、ケースに入れてチェーンやストラップをつけキーホルダーのようにつけて持ち歩くことが想定されています。
さらに、市区町村で独自の要素を追加することもできるなど運用方法が一部異なっています。ヘルプカードをもらいたいと考えている方は、ご自身のお住いの役所などに確認してみるといいでしょう。

出典:(ヘルプマークとヘルプカードについて|滋賀県ホームページ)

ヘルプマークの使い方・記入例は?
ヘルプマークは周りの人に気づいてもらう使い方をすることが大事です。ストラップ仕様になっているため、キーホルダーのようにかばんなどの周囲から見える場所につけて使うという方が多いようです。実際に駅などで目にしたことがある方もいると思います。
また、ヘルプマークの裏面には必要な情報を記載できるシールを貼れるようになっています。
ヘルプマークの記入例として以下のような書き方があります。
- 名前:○○(本人の氏名)
- 緊急連絡先:00-0000-0000(かかりつけの病院と主治医の名前)
- 血液型:●型(本人の血液型)
- 薬について:○○と△△を服薬中(服薬中の薬の名称)
- アレルギーの有無:○○(アレルギーがあれば記載)
- 手伝ってほしいこと:発作を起こしたときは緊急連絡先へ電話をお願いします
ほかの人が見ることもあるため、個人情報などは無理せずに、書ける範囲で記入するようにしましょう。
ヘルプマークのスペースは限られているため「一番周りに知らせたいこと」を記載することがポイントです。
また、一例として、ヘルプマークの裏面に「発作が起こることがあります。リュックの中に症状について書いたヘルプカードが入っているので見てください」と書いておいて、ヘルプマークからヘルプカードへ誘導する方法もあります。
発達障害のある方の記入例
ヘルプマークを見る方は障害の知識がない場合も多いため、障害の名称などだけではなくどんなことに困って、どういった対応をしてもらいたいかを記載しておくことが大事です。
例えば発達障害のある方の記入例でいうと、
- 読み書きが苦手なため、分からない言葉があったときに教えてください
- 会話を理解するのが苦手なため、ゆっくりと一言ずつ話してください
- パニックになったときには、静かな場所に誘導してください など
といった形で、困ることと対応方法を記入するといいでしょう。
ヘルプマークを身につけるとどんな配慮が得られる?
ヘルプマークを身につけることで、困った場面で以下のような配慮を受けることもできます。
- 困りごとを上手く言葉で話せないときも、ヘルプマークの裏面を見せて伝えらえる
- 周りの方から「困っている」という状況に気付いてもらいやすくなる
- 突発的な出来事が起こったときに、声をかけてもらいやすくなる
- 災害時など避難が必要な状況のときに、支援を得やすくなる
- 長時間立ち続けることが困難な場合に、電車やバスなどで席を譲ってもらいやすくなる など
ヘルプマークの使用例
実際に下記のような場面でヘルプマークが役に立つことがあります。
急な発作が起きたとき
持病や病などで、突然発作が起きた場合に備えて、あらかじめヘルプマークに連絡先や必要な支援内容を記載しておくことで緊急の場合でも適切な処置や支援を受けられる可能性があります。
子どもが人混みで困ったとき
子どもが人通りの多い駅構内などの混雑している場所などでストレスを感じ、具合が悪くなってしまうといった場合に、あらかじめ見えやすいところに支援方法などを記載したヘルプマークをつけておくことで、周りの人から手助けを受けたり、落ち着ける場所まで案内してもらえる可能性があります。
人混みが苦手な子どもの場合
人通りの多い駅構内などの混雑している場所などでストレスを感じ、具合が悪くなってしまうといった場合に、あらかじめ見えやすいところに支援方法などを記載したヘルプマークをつけておくことで、周りの人から手助けを受けたり、落ち着ける場所まで案内してもらえる可能性があります。
電車やバスの優先席を利用する必要があるとき
持病や障害により疲れやすく、電車やバスなどで座りたい場合にヘルプマークを身につけておくことで視覚的に伝えやすくなります。
また、ヘルプマークを目立つところに身につけておくことで、「優先席に座ると注意を受けてしまうかもしれない」といった不安を和らげることにもつながる可能性があります。
子どもが迷子になったとき
発達障害や知的障害のある子どもの中には、道に迷ってしまったときや迷子になったときに自力で家に帰ることが困難な場合があります。そのようなときに備えてヘルプマークを身につけておくことで、周りの人が案内をしてくれたり、連絡をしてくれる可能性が高まるでしょう。
ヘルプマークのまとめ

ヘルプマークは、外部からは見えづらい困難があって、配慮や援助を必要とする方が利用できるマークです。
ヘルプマークは医師の診断書や障害者手帳の有無にかかわらず、無料で受け取れるため、街中やお店、電車などでよく困りごとが起こる場合や不安がある場合、一度ヘルプマークを活用してみてもいいかもしれません。
また、ヘルプマークよりも多くの情報を記入できる「ヘルプカード」の利用もご検討ください。
ヘルプマークには対象となる病気の一覧があるわけではありません。もしも「自分の症状でヘルプマークを身につけてもいいのだろうか?」などの不安がある場合は、窓口(お住まいのエリアの市役所など)に問い合わせてみましょう。









