
子どもが「急に明るい場所に出ると目を痛そうにする」「蛍光灯などのチカチカした光に過敏に反応する」といったことが頻繁にあり、視覚過敏があるかもしれないと感じている方もいるのではないでしょうか。
視覚過敏とは目に入ってくる刺激に過剰に反応してしまう状態で、日常生活や学校などでさまざまな困りごとが起こる可能性があります。
視覚過敏は個人差が大きいため、サングラスやパーティションを使用して刺激を減らすなどその子の状態にあわせた環境調整や対策をして、困りごとを減らしていくことが大切です。
この記事では視覚過敏の原因や症状、家庭や学校でできる対策や困ったときの相談先を紹介します。
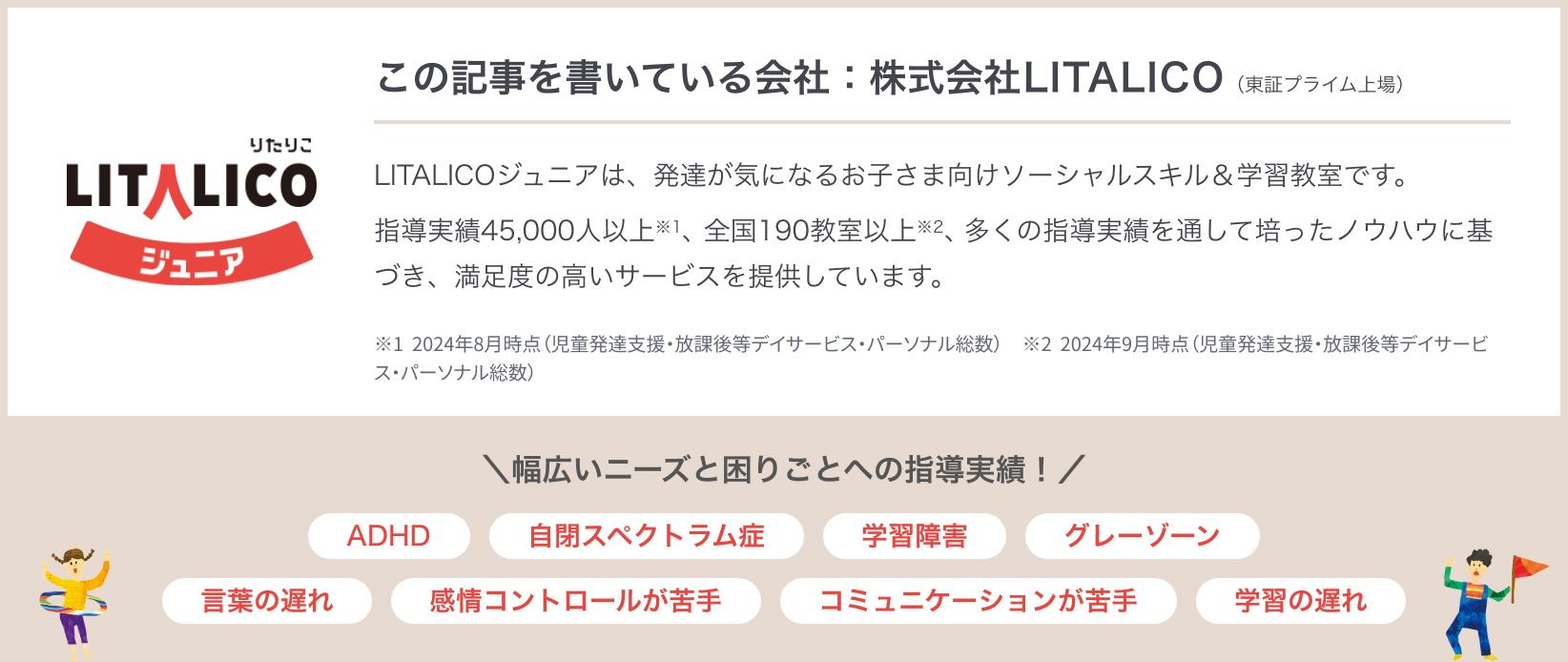
視覚過敏とは?
視覚過敏とは、光や色、物の動きなど、目から入る刺激が過剰に感じられ、苦痛や不快感を伴い、生活に不便が生じる状態のことを指す言葉です。
視覚だけではなく、「入ってくる刺激が過剰に感じられて苦痛や不快感を伴う」ことは、聴覚、視覚、触覚、味覚、嗅覚などあらゆる感覚に対しても起こる場合があり、これらを「感覚過敏」と呼びます。医学的な診断名ではなく、感覚が過敏になっている状態を指す言葉です。反対に、感覚が非常に鈍感で不便があることもあり、これを感覚鈍麻(どんま)と呼びます。
刺激をどのように感じるかは、その人の脳の受け取り方によって違うため、感覚過敏や鈍麻の現れ方も、人によって異なります。視覚だけ、聴覚だけ、などひとつの感覚だけに過敏や鈍麻が見られる場合もあれば、複数にわたって生じることもあります。
例えば視覚過敏のある方では「チカチカした光がまぶしくて見られない」「人混みなど視覚刺激が多い場所にいると気分が悪くなる」「特定の色を見つめていられない」などの困りごとが生じる場合があります。
このように個人差が大きいため、子どもがどのようなことで困っているかを把握し、その子に合った環境調整やツールを使うなどの対策を行っていくことが大事です。
視覚過敏の特徴
視覚過敏は感覚過敏の一つで、目から入ってくる刺激に過剰に反応してしまう特徴があります。
視覚過敏のある子どもの困りごとには以下のようなものがあります。
- 太陽の光などまぶしい光のもとでは正面を見ていられない
- 真っ白な紙を見つめていられない
- チカチカ光る蛍光灯が見られない
- 人混みや物が多い場所ではひどく疲れてしまう
- 一度に多くの情報が目に飛び込んできて辛くなる
- 部屋の明かりが気になり夜なかなか眠れない
- 文字を追うのが難しくて本を読むのを嫌がる
- 集中して目を使うと、頭痛や吐き気を訴える
視覚過敏といっても人によって感じ方は異なります。今挙げた例も参考として捉えていただければと思います。
視覚などの感覚は他の人と共有できないため、視覚過敏のある子どもはどういったことで困っているのか周りの大人からは分かりづらいということがあります。
また、子ども自身もその感覚でずっと過ごしてきたため、「ほかの人と感覚が異なる」ということや「自分に視覚的な過敏さがある」ということがすぐには飲み込めないことがあります。
視覚過敏の原因

現時点で視覚過敏の原因ははっきりと分かっていませんが、以下のような複数の要因が関連すると考えられています。
目の疾患
目に何らかの疾患があって、視覚が過敏になっている場合があります。角膜炎などは明るい光を見ると目が痛くなる場合があるため、目の疾患が気になる場合は眼科を受診してみるといいでしょう。
脳の機能
脳の機能が要因となって視覚過敏が生じていることも考えられます。その場合の脳の機能としては、発達障害やてんかん、片頭痛などが考えられます。
発達障害
発達障害は先天的な脳の機能の偏りが原因の一つと考えられている障害です。
アメリカ精神医学会の診断基準『DSM-5‐TR』(精神疾患の診断・統計マニュアル)において、発達障害の一つであるASD(自閉スペクトラム症)における特性の一つとして視覚過敏など感覚の過敏性が記載されています。
ただし、視覚過敏があるからといって発達障害があるとは言えません。可能性として考えられるということですので、発達が気になる場合は後ほど紹介する専門機関に相談してみるといいでしょう。
てんかんや片頭痛
てんかんや片頭痛があることによって、脳の神経細胞が過敏な状態になり、それが光をまぶしく感じる視覚過敏などの感覚過敏を起こしている可能性があります。
こちらも、感覚過敏があるからといっててんかんや片頭痛とは判断できないため、かかりつけの小児科や支援機関に相談をしてみるといいでしょう。
ストレスや不安
子どもがストレスや不安を抱えていると、それが脳に影響して視覚過敏などの感覚過敏が生じている可能性があります。
ストレスや不安によって元々ある過敏性が増していることもあるため、子どものストレスや不安を軽減させる対策をとっていくことが大事です。
視覚過敏の症状
ここでは視覚過敏の症状について紹介します。
視覚過敏は光や色、物の動きといった視覚情報に対する過敏性または過敏さがある状態を指します。
視覚過敏のある方の感じ方の例として、
- 太陽の光が鏡に反射したように目を開けていられないほどにまぶしく感じられる
- 書かれた文字が動いたり歪んだりして見える
- 紙や画面の白い部分が光っているように見えて書かれた文字が読みづらい
- 特定の色が強く感じられる
- 目で見た情報が一度に頭に入ってくる感覚がある
などがあります。
こういった症状は個人差が大きく、心身の状態によっても変わることがあります。
視覚過敏は周りからはわかりづらく、視覚過敏のある子どもはその感覚でずっと生きてきたため、他の人と見え方が異なることにも気づいていない場合があります。
インターネット上では視覚過敏のセルフチェックや診断テストといったものも見られますが、それだけでは判断できないため、子どもに気になる様子がある場合は専門機関に相談するようにしましょう。
視覚過敏の対策は?

ここでは視覚過敏のある子どもの困りごとを軽減させる対策を紹介します。視覚過敏を無理に変えようとしても、そのことがストレスとなり悪化することも考えられます。視覚から入る刺激自体を軽減する工夫をしていくことが大切です。
視覚過敏対策のアイテムを使用する
視覚過敏のある子どもの困りごとを減らすために、視覚から入る刺激を減らしていくアイテムを使用する対策法があります。
例えば、光がまぶしく感じられる子どもには、サングラスをかけることで刺激を和らげていくことができます。ほかにも、偏光グラスといって光の反射を抑えるメガネもあります。
また、人混みや物の多さが気になる子どもには、サンバイザーやつばのある帽子を使って、視界から入る情報を制限する方法もあります。
子どもが安心できる物を持たせておく
視覚過敏などの感覚過敏は、ストレスや不安などの心の状態でも度合いが変化することがあるため、子どもがなるべく安心できるような対策をすることが重要となります。
その一つとして外出時に「子どもが安心できる物を持たせておく」ことも有効です。
例えばお気に入りのぬいぐるみだったり、毛布やブランケットなど感覚的に安心できる物を持たせておくと不安を軽減することにつながります。
子どもが小さいうちは、保護者が持っていてすぐに渡せるようにするのもいいでしょう。
見通しが立つように説明する
視覚過敏などの不安を軽減させる方法として「見通しが立つように説明する」方法もあります。
刺激があるとあらかじめわかっていれば、子どもも心の準備ができるようになります。
「これからまぶしい場所に出るよ」「人が大勢いる場所にいくけど、何時には帰るからね」「つかれたらここで休憩するようにしようね」と、これから刺激があることと、いつ刺激が終わるか、休憩できる場所はあるかといったこともセットで伝えられると安心感も増します。
言葉だけでなく絵や写真を使って予定や手順を伝えるなど、子どもに合った方法で伝えていくといいでしょう。
家の中の環境を整える
家の中の環境を整えることも視覚過敏のある子どもが過ごしやすくなるために大切です。
子どもの部屋のインテリアを「シンプルな色にする」「物を極力減らす」ことや、照明を「間接照明にする」といった対策で刺激を減らしていく方法があります。寝付けないことが多い場合は、カーテンを「遮光カーテンにする」「ほかの部屋からの明かりが入らないようにする」といった工夫をしてみてもいいでしょう。
ほかにも家の中に四方が囲まれた刺激の少ない空間を作っておいて、子どもが「ここにいれば刺激が少なくてすむ」と安心できる場所を用意しておくと、安心感が増して生活しやすくなることもあります。
学習しやすくなるツールの活用や機器の設定をする
視覚過敏の影響で学習に困りごとが出ている場合は、ツールの活用や機器の設定で視覚から入る刺激を軽減していく方法もあります。
例えばパソコンやタブレットの画面が苦手な子どもの場合は、
- ブルーライトカットメガネを使用する
- 画面にブルーライトカットシートを貼る
- 設定で画面の「輝度」を下げる(低刺激モードなどが用意されている機器もあります)
- 音声読み上げ機能を使って画面を見る時間を減らす
- といった対策があります。
ほかにも真っ白な紙がまぶしくて文字が読みにくいときは
- 色のついた半透明の下敷きを上に当てる
- 下敷きや定規で必要な部分以外を隠しながら読んでいく
- テスト用紙は反射の少ない紙に印刷してもらう
- といった方法があります。
子どもの視覚過敏の困りごとにあわせてツールなどの活用を検討してみるといいでしょう。
学校や園で配慮をお願いする
ここまでは主にご家庭でできる視覚過敏への対応を紹介しました。学校や園では子どもについて必要な合理的配慮を相談する方法もあります。
合理的配慮とは障害のある子どもが勉強などをする上で困難となっていることを、学校などができる範囲で解消していくことです。
合理的配慮の例としては以下のようなものがあります。
- 光の強さなどが刺激にならない席にしてもらう
- 席にパーテーションをおいてもらう
- 気分が悪くなったときにクールダウンできる場所を確保してもらう
- テストは別室で受けさせてもらう
視覚過敏は、他の過敏性と併存する場合が多いので、それと合わせた配慮を相談するといいでしょう。
学校で合理的配慮をお願いする場合には、担任の先生や学年主任、またはスクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラーといった方に相談してみるといいでしょう。
視覚過敏のある子どもの相談先は?
子どもが視覚過敏などの感覚過敏がある場合に、相談できる支援機関などを紹介します。
眼科
視覚過敏自体は病気ではありませんが、目の病気が要因となって視覚過敏のような状態になっている可能性もあります。
例えば角膜炎の影響により明るい光を見ることで痛みが生じている場合もあるため、眼科で検査してもらうことも大事です。目の疾患が原因で視覚過敏が起きている場合は、疾患の治療により視覚過敏も改善することもあります。
保健センター
保健センターは地域の住民の保険や衛生に携わる行政機関で、子どもの健康に対する相談の受け付けや1歳半検診・3歳児検診なども行っています。
保健師などの専門家が相談に対してアドバイスや、視覚過敏の状態を聞いて適した医療機関や支援機関の紹介などを行ってくれることがあります。
児童家庭支援センター
児童家庭支援センターは子育てに対する相談に対して必要な助言、指導を行っている場所です。地域によっては子ども家庭支援センターなどとも呼ばれています。
視覚過敏があるなどの悩みを相談することができ、状況に応じて児童福祉施設など関係する支援機関との連絡調整も行っています。
児童発達支援センター
児童発達支援センターは、主に障害のある子どもに対して身近な地域での支援を行う機関です。
日常生活や学校生活で困難がある子どもに対して、日常や集団生活での過ごし方などのさまざまなプログラムを提供しています。未就学児を対象とした「児童発達支援」、就学児を対象とした「放課後等デイサービス」といった支援があります。
児童発達支援や放課後等デイサービスを利用するには自治体に申請をして「通所受給者証」の交付を受ける必要がありますが、障害の診断や障害者手帳は必須ではありません。
LITALICOジュニアでは児童発達支援、放課後等デイサービスを運営しています。
視覚過敏をはじめとした感覚過敏があって、学習や日常生活に困りごとがある子どもへの支援や特性を踏まえて学校への配慮事項を一緒に考えるサポートなども行なっています。
通所受給者証がなくても利用できる学習塾形式の教室もありますので、子どもが視覚過敏など感覚過敏があるという方はぜひ一度ご相談ください。
視覚過敏のまとめ
視覚過敏のある子どもは「眩しい光で目が痛くなる」「真っ白な紙を見つめられない」「視覚情報が多い場所では疲れてしまう」など、日常生活や学校生活などで困る場面があります。
視覚過敏と一口に言っても、人によって感じ方は大きく異なります。また、ほかの感覚過敏も一緒にある場合もあります。
視覚過敏という言葉にとらわれるのではなく、どういったことに過敏を感じて困っているのかを把握して、その子に合った対策をしていくことが大事です。
ご家庭だけでは難しいこともあると思いますので、学校や支援機関などと連携しながら子どもにとって生活や学習がしやすい環境を整えていくようにしていきましょう。
-

監修者
鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授/LITALICO研究所 客員研究員
井上 雅彦
応用行動分析学をベースにエビデンスに基づく臨床心理学を目指し活動。対象は主に自閉スペクトラム症や発達障害のある人たちとその家族で、支援のための様々なプログラムを開発している。









