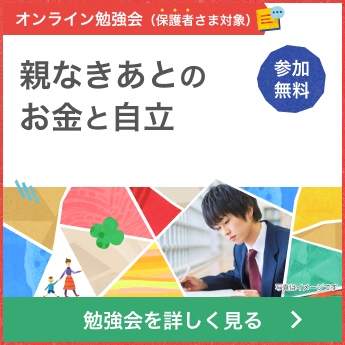子どもに障害があり日常生活で困りごとを感じる方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。そんなときに利用できるサービスの1つが「障害福祉サービス」です。
子どもに障害があって日常生活で困っている場合の支援として、「児童福祉法」を思い浮かべる方も多いと思います。
しかし、児童福祉法のサービス以外にも以外にも子どものホームヘルプやショートステイなどが使用できる「障害福祉サービス」があります。
障害福祉サービスは障害者総合支援法という法律を基にして障害のある大人や子どもへさまざまなサービスを提供しています。
この記事では、障害福祉サービスの一覧や受給者証の取得、サービス利用までの流れなどをわかりやすく解説します。
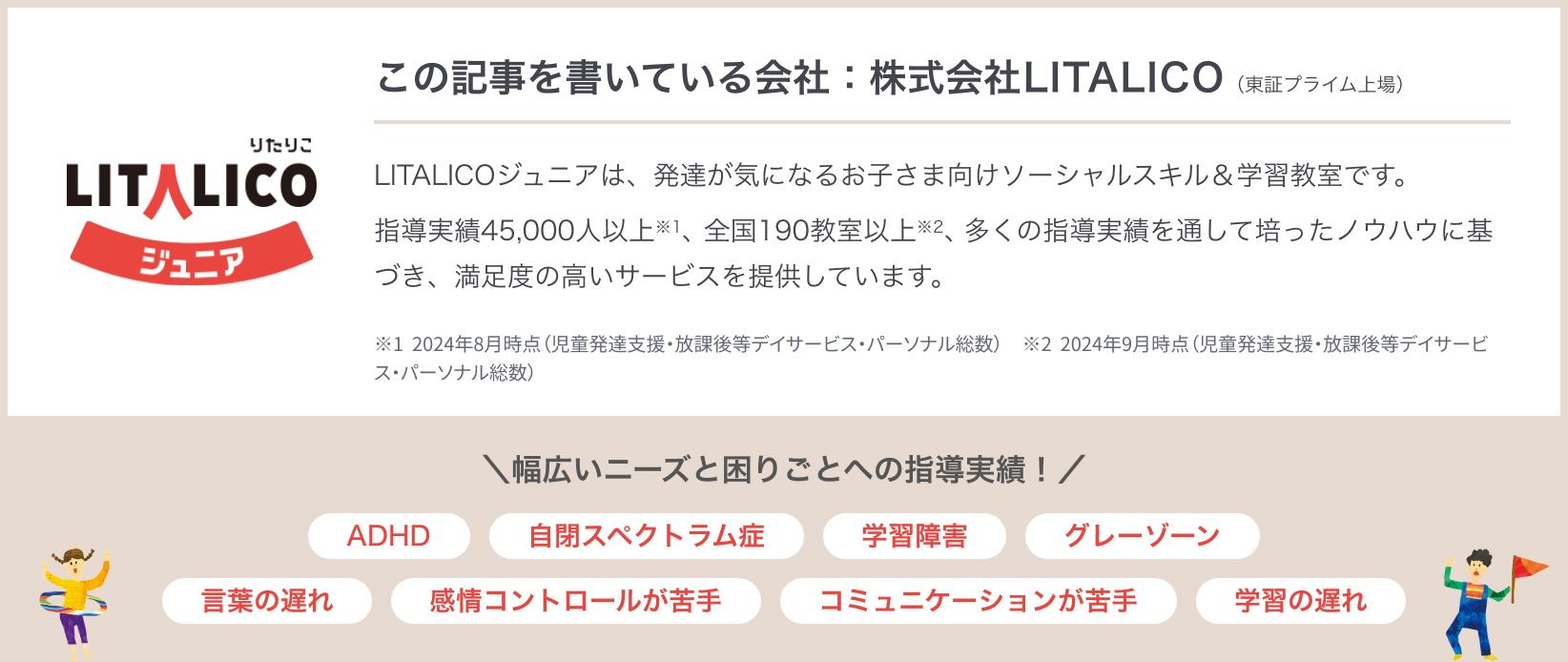
障害福祉サービスとは?
障害福祉サービスとは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下:障害者総合支援法)」に定められた、障害や一部の難病のある方への支援のことです。
障害のある方といっても一人ひとり困っていることは違ってきます。自宅で介護が必要な方、施設での介護が必要な方、移動に援助が必要な方、就職に支援が必要な方などさまざまです。
障害福祉サービスは、そういったさまざまなニーズに対して、その人の状況を判断して必要な支援を提供しているサービスです。
障害福祉サービスには大きく分けて、「介護給付」と「訓練等給付」があり、それぞれに具体的なニーズに応える複数のサービスがあります。
障害福祉サービスは、比較的成人に向けたサービスの数が多くなっていますが、ホームヘルプやショートステイなど子ども向けのサービスも展開しています。子ども向けの支援には児童福祉法もありますが、それぞれ違いがありますので、その子の状況にあったサービスを利用していくといいでしょう。
なお、障害福祉サービスは法律に基づくサービスですが、運営は自治体が行っているため、運営する自治体によっては障害が異なる場合があります。詳しいことはお住いの自治体の障害福祉窓口などにお尋ねください。
障害福祉サービスの対象者
障害福祉サービスは法律によって対象者が決まっています。
障害福祉サービスの対象者一覧
- 身体障害者
- 知的障害者
- 精神障害者(発達障害者を含む)
- 難病など一定の障害のある方(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者)
上記ように、発達障害のある方も障害福祉サービスの対象になります。
対象者自体に年齢制限などは設けられていません。ただ、この後紹介する障害福祉サービス一覧の中では、年齢や障害によって利用できるサービスが異なってきます。
なお、対象となる難病については決まった疾患があるわけでなく、定期的に見直しが行われています。
詳細は厚生労働省のサイトをご確認ください。
障害福祉サービス一覧
先ほどご紹介した通り、障害福祉サービスには大きく分けて「介護給付」と「訓練等給付」があります。

訓練等給付については、基本的に就職に関するサービスが多く、障害のある子どもは対象とされていません。
そのため、ここでは子どもが対象となるサービスも多い介護給付の内容を中心にご紹介します。
介護給付とは
介護給付とは、在宅で介護を受けたり(ホームヘルプ)、施設に入所(ショートステイなど)したりなどの生活をサポートするためのサービスのことです。
その中にも「訪問系」と「日中活動系」、「施設系」のサービスがあるので順番に紹介していきます。
介護給付の訪問系サービス
- 居宅介護(子どもも対象)
- 重度訪問介護
- 同行援護(子どもも対象)
- 行動援護(子どもも対象)
- 重度障害者等包括支援(子どもも対象)
居宅介護とは、住んでいる家などを訪問して、入浴や排せつ、家事補助など生活全般にわたる援助を行います。ホームヘルプとも呼ばれています。障害のある子どももサービスの対象となります。
重度訪問介護とは、常に介護を必要とする肢体不自由・知的障害(知的発達症)・精神障害のある方に関して生活全般へ援助を行うサービスです。
同行援護とは、視覚障害のある方に対して移動する際に必要な情報の提供や声掛けなどを行うサービスのことです。障害のある子どもも利用が可能です。
行動援護も障害のある子どもも対象となるサービスで、知的障害(知的発達症)または精神障害のある方が、外出など行動する際に危険を回避するための情報提供や援助などを行います。
重度障害者等包括支援とは、常に介護を必要とする重度の障害がある方に、居宅介護など以下の複数のサービスが包括的に提供されます。こちらも障害のある子どもも対象となっています。
- 居宅介護
- 重度訪問介護
- 同行援護
- 行動援護
- 生活介護
- 短期入所
- 共同生活援助
- 自立訓練
- 就労移行支援
- 就労継続支援
介護給付の日中活動系サービス
- 療養介護
- 生活介護
- 短期入所(子どもも対象)
- 療養介護
療養介護とは病院などの医療機関に長期間入院しており、医療とあわせて常に介護を必要とする方に対するサービスです。主に日中にリハビリなどの機能訓練、入浴や排せつ、日常生活上の相談支援などを提供します。
生活介護とは常に介護を必要とする障害のある方が、障害者支援施設などに通所するサービスのことです。主に昼間に、身体介助、家事援助、生活に関する相談などの支援などを提供するほか、創作活動の機会の提供や身体機能向上のための援助などを行っています。
短期入所はショートステイとも呼ばれ、普段家族などで居宅介護をしている際に何らかの理由で難しい状況で、障害のある方が障害者支援施設などへ短期間入所するサービスのことです。入浴や排せつなどの介助や見守りなどを行います。障害のある子どもも利用可能です。
介護給付の施設系サービス
施設入所支援では、施設に入所している障害のある方に対して、主に夜間に身体介助や食事の提供、健康管理などのサービスを提供しています。
訓練等給付とは
訓練等給付とは、障害がある方が自立した生活や社会生活を送るために必要な訓練の機会を提供するサービスのことです。
訓練等給付のサービスは以下があります。
【居住支援系】
- 自立生活援助
- 共同生活援助
【訓練系・就労系】
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型)
- 就労継続支援(B型)
- 就労定着支援
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
障害福祉サービス受給者証とは?

障害福祉サービスを受けるためには、「障害福祉サービス受給者証」(以下、受給者証)を取得する必要があります。
障害福祉サービスは障害者手帳がないと利用できないと思われる方もいらっしゃいますが、障害者手帳を取得していない場合でも、この受給者証を取得できる可能性があります。
受給者証は自身で手続きをすることが、取得の条件となっています。手続き先はお住いの自治体の障害福祉課(自治体によって名称が異なる場合があります。)なので、気になる方は問い合わせてみるといいでしょう。
障害福祉サービス利用の流れ

障害福祉サービスの申請場所や申請から利用までの流れについて解説します。
ここでは、介護給付の申請の手続きについてご紹介します。
介護給付の利用の流れ
介護給付利用までの流れを紹介します。ここでは、東京都の流れを基に記載していきます。
1.相談・利用申請
サービスの利用を希望する障害のある方、または保護者はお住まいの自治体の窓口または相談支援事業所にその旨を相談します。
その後アドバイスや施設見学などをしたうえで利用したいサービスが決まったら、障害福祉サービス利用の申請を行います。
2.サービス等利用計画案の作成と提出
どのような期間でどういったサービスを利用するのかといった利用計画を作成します。
計画案は利用する本人が作成することもできますが、作成が難しい場合は、指定相談支援事業所に作成を依頼するのが一般的です。
3.認定調査
心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査が行われます。
調査では、障害者の心身の状況を把握するための80項目の調査や介護者の状況、本人の日中活動の状況、居住についてなどの聞き取りが行われます。障害のある子どもについては調査項目が一部異なる場合があるようです。
4.障害支援区分の認定
申請した自治体の審査会で、これまでの状況を総合的に判断して障害支援区分の認定が行
われます。
5.サービス等利用計画案の提出
2で作成したサービス等利用計画案を、申請をした市区町村の窓口に提出します。
6.支給決定・受給者証の交付
審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容をふまえて、支給決定が行われると、受給者証が交付されます。
7.サービス事業者と契約
利用したいサービスを提供する事業所を選んで、サービス利用契約を行います。
これで障害福祉サービスの利用が正式に開始されます。障害福祉サービス利用までの手続きには2か月程度かかる可能性があるので、検討されている方は早めに一度相談しに行くといいでしょう。
障害福祉サービスの利用者負担
障害福祉サービスを利用する際には、利用料がかかる場合があります。これを利用者負担と呼んでいます。
サービスにかかった全額を支払うわけではなく、世帯所得に応じて4つの区分に分けられ、それぞれにひと月の上限額が決まっているので、それ以上支払うことはありません。
以下、4つの区分とそれぞれの負担額です。
- 生活保護世帯:負担額0円
- 市町村税非課税世帯(おおむね世帯収入300万円以下):負担額0円
- 市町村税課税世帯で世帯収入おおむね670万円以下:月負担上限9,300円
- 上記以外の世帯:月負担上限37,200円
障害福祉サービスの探し方
障害福祉サービスにはさまざまな種類があり、またその種類ごとにサービスを提供する事業所も複数あります。
その中から子どもに合ったサービスを探すのは大変です。そういった場合に活用できるサービスの探し方を紹介します。
障害福祉サービス等情報検索サイト
インターネット上に、住所、事業所名、サービス種別から利用したいサービスを検索することができるサイトがあります。
マップでも事業所の場所が確認できるので、お住まいからお近くにどんな事業所があるか確認することもできます。
障害福祉サービス以外に子どもが対象となる支援

ここまでご紹介した障害福祉サービスは主に大人向けのサービスが多かったですが、ここでは障害のある子どもが利用できる支援やサービスについてご紹介します。
子どもが活用できる支援としては、児童福祉法に基づいて以下のような支援があります。
児童発達支援
児童発達支援は、障害のある未就学の子どもを対象とした児童福祉法に基づく通所支援のひとつです。
障害や発達の遅れなどがある子どもが通所し、日常生活や社会生活を円滑に営めるように、さまざまなサービスを提供しています。
例えば、生活能力の向上のために必要な動作の訓練や、集団生活へ適応するためのトレーニングなどの支援が行われます。
放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、障害のある小学校に入学する6歳から18歳までの就学児の子どもを対象とした児童福祉法に基づく通所支援のひとつです。
放課後等デイサービスは、児童発達支援と行われる内容に大きな違いはなく対象の年齢が異なります。
保育所等訪問支援
障害のある子どもが集団生活に適応することができるように、専門のスタッフが子どもが通う保育所、幼稚園、小学校などを訪問し、子どもに対して集団での生活に必要なサポートを行ったり訪問先施設のスタッフに対して支援方法等の助言などを行います。
障害児入所支援
障害のある子どもが施設に入所して、生活をおくる上で必要な知識やスキルを身に付けるためのトレーニングなどの支援が行われます。
発達の気になる子どもの学習塾
LITALICOジュニアでは、発達障害や発達の遅れが気になる子どもの支援を行っています。
各地で児童発達支援事業所、放課後等デイサービスを展開し、一人ひとりのニーズや特性に合わせて学習やソーシャルスキルアップをメインとした授業で子どもの成長をサポートをしています。
LITALICOジュニアでは幼児教室・学習塾も運営しております。こちらの教室は受給者証がなくても利用でき、通所できない子ども向けのサービスとしてオンライン支援を行っています。
無料での相談や体験も実施しておりますので、子どもの発達が気になる方は一度お問い合わせください。
障害福祉サービスのまとめ

障害福祉サービスとは、障害のある方が利用できるさまざまな支援のことです。
障害福祉サービスには大人向けのサービスがメインですが、子どもが利用できるサービスも多くあります。児童福祉法のサービスと組み合わせることで、子どもにより良い支援を提供できる可能性もあります。
障害福祉サービスの利用を検討している方は、自治体の窓口や相談支援事業所へ相談してみるといいでしょう。また、インターネットでも事業所を検索できるサイトがありますので、活用してみるのもいいでしょう。
障害福祉サービスについて、大人向けの記事はこちらでご紹介していますので、気になる方はご覧ください。