
ディスグラフィア(書字障害)は、文字や文章を書くことに困難が生じる症状で、SLD(限局性学習症)の種類の一つです。
子どもの学習において、他の科目は問題ないのに、文字を書くことだけがうまくできない様子がある場合は、ディスグラフィアが関係している可能性があるかもしれません。
ディスグラフィアがある場合は、ただ字を書く練習を繰り返しても効果は期待できないため、特徴に合った支援をおこなうことが大切です。
この記事では、ディスグラフィアの特徴や困りごと、原因や支援方法について説明します。
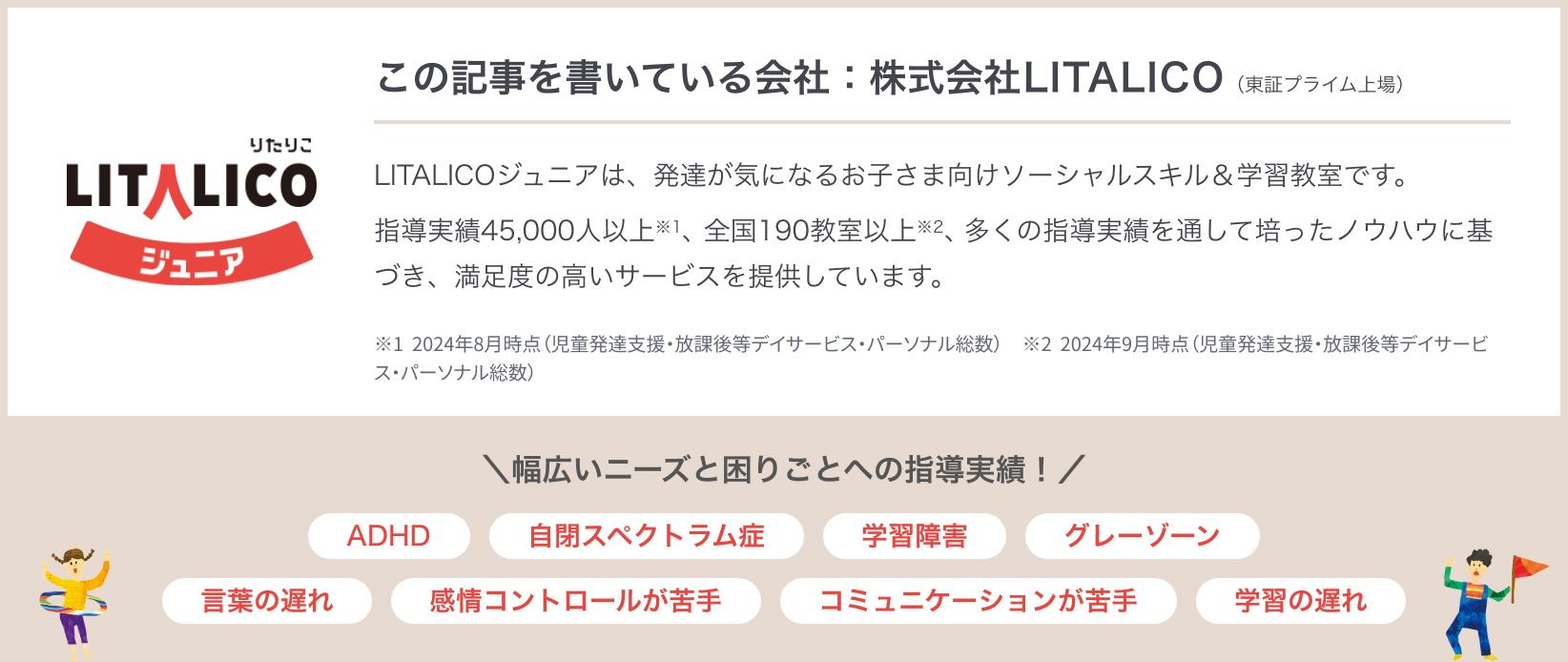
ディスグラフィア(書字障害)とは?

ディスグラフィア(dysgraphia)は、文字や文章などを手書きすることなどに困難が生じる症状のことです。
しかし「ディスグラフィア」は医学用語ではなく、統一された定義もありません。
SLD(限局性学習症)には、以下の3つの種類があります。
- 読字の障害(ディスレクシア):「読む」ことに困難がある
- 書字表出障害(ディスグラフィア):「書く」ことに困難がある
- 算数障害(ディスカリキュア):「算数・計算」に困難がある
文字を書くためには、まず文字を認識する必要があるので、「読字障害(ディスグラフィア)」がある子どもは、書くことにも影響が見られます。
「怠けている」「やる気がない」のではない
SLD(限局性学習症)は、知的発達に遅れがない場合にも生じることがあります。
このため、ディスグラフィアを含むSLD(限局性学習症)のある子どもは勉強において、「聞いて、理解する」や「答える」など、読み書きや算数が直接関わらない部分では問題が生じていなかったりします。
つまり「がんばっているのに、結果が出にくい」状態であり、子ども自身も困っていたり、自分を責めていたりすることがあります。特性が理解されないまま、「困った子」「できない子」として誤解され、叱られることで、やる気や自信をなくしてしまいがちです。不登校や引きこもり、うつ、反抗挑戦性障害といった二次的な問題を防ぐためにもこれらの兆候を見逃さないことが重要です。
子どもが困っている場合は、周囲の大人が早い段階で気づいて適切な支援をおこなうことが大切です。
ディスグラフィア(書字障害)の特徴や困りごと

ディスグラフィアの症状は原因によっても異なるため、子どもによってさまざまな特徴の現れ方があります。
ここでは、ディスグラフィアのある子どもが示すことのある特徴や困りごとの例を紹介します。
ディスグラフィア(書字障害)の特徴
文字を書くとき、私たちは文字の形や大きさ、ほかの文字との違いなどを識別して書いています。
しかし、ディスグラフィアのある子どもはこれらの識別が苦手なため、以下のような特徴が現れる傾向があります。
- 言葉と意味を理解していても、その文字を正しく書けない
- 漢字の「へん」と「つくり」を逆に書く
- 漢字の線(画)が足りない/多い
- バラバラだったり、バランスの悪い文字を書く
- 文字の書き順が不自然
- 上下はそのままで、左右が反転した「鏡文字」を書く
- 「ね」と「ぬ」、「ン」と「ソ」などの似ている文字を間違えて書く
- 文字の書き取り練習のとき、文字の形が乱れたり、マス目からはみ出してしまう
- 「て」「に」「を」「は」などの接続詞の使い方など、文法の間違いが多い
ディスグラフィア(書字障害)の困りごと
ディスグラフィアの特徴は勉強の場面において、以下のような困りごとにつながることがあります。
- 書くのに時間がかかるため、先生が黒板に書いた文字をすべて写す前に消されてしまう
- 文字を書くのに努力がいるため、長文が書けず、短文になってしまう傾向がある
- 文法の間違いが多いため、意味の通じない文章を書いてしまう
- 国語の教科が苦手
- テストでよい点数が取れない
ディスグラフィア(書字障害)の困りごとにアプローチできる発達支援LITALICOジュニア
お子さまの発達支援教室「LITALICOジュニア」では、「字のバランスが悪い」「板書が苦手」「文法の間違いが多い」などでお困りのディスグラフィアのお子さまへの指導実績も豊富にあります。
お子さまの「楽しい!」を大切にし、お子さま自身が自発的に「やりたい!」「知りたい!」と思えるように授業を進めていくので、学習意欲が下がってしまっているお子さまにもおすすめです。
お子さまがどの部分でつまずいているか丁寧に確認し、一人ひとりに合った学習方法でサポートします。
首都圏25教室・2万件以上の指導実績があり、全国から受講できるオンラインでの個別授業も実施しています。
気になる方はお気軽にご相談ください。
ディスグラフィア(書字障害)の原因は?

ディスグラフィアを含むSLD(限局性学習症)の原因ははっきりと分かっていませんが、脳機能の偏りであると考えられています。
目や耳などの感覚器官から入ってきた情報を脳が処理する過程を「認知」と呼びますが、この認知の過程のどこかに偏りがあるとされます。
具体的には、主に以下のような要素が関係しているとされています。
視覚認知力の弱さ
視覚から入ってきた情報を処理する機能が弱い場合は、文字の形や位置を認識することが難しくなります。
すると文字のパーツがなかなか覚えられず、文字を正確に書くことが難しくなります。
音韻処理力の弱さ
音韻処理とは、言葉を構成するそれぞれの音である「音韻」を、脳が処理する働きのことです。目で見た文字と音(音韻)を関連づけたり、逆に音から文字を想起したりします。
この音韻処理の力に弱さがある場合は、文字から音に直す「読み」や、音から文字にする「書き」の困難が生じる場合もあります。
そのため、ディスレクシア(読字障害)のある子どもにおいて、書くことの困難が生じる場合もあります。
協調運動の障害
協調運動とは体のさまざまな部位を同時に動かして協調させることで、脳がその指令を出しています。
協調運動が苦手な場合は手先を細かくコントロールすることが難しいため、文字がうまく書けないことがあります。
ディスグラフィア(書字障害)のある子どもへの支援方法

ディスグラフィアが原因で文字をうまく書けない場合は、ただ文字を書く練習を繰り返しても効果は期待できません。
ディスグラフィアのある子どもの特徴は一人ひとり異なるため、特徴や、ディスグラフィアの原因にあわせた支援をおこなうことが大切です。
ここでは、ディスグラフィアのある子どもに対する支援方法の例を紹介します。
特徴に合った練習
以下のような練習や工夫の方法があります。
ただし、これらの方法で必ずうまくいくわけではなく、書くことが逆に難しくなる場合もあります。
したがって、さまざまな方法を試しながら、子どもに合う方法を見つけていくことが重要です。
文字の形を覚えるのが苦手な場合の練習方法
・「なぞり書き」ができる練習帳やドリルなどを使う
・漢字の構成要素を声に出して言いながら書く
・漢字をイメージで覚える。例:「杉」であれば「木と3本のヒゲ」など
文字のバランスが乱れる場合の練習方法
・マス目の入ったノートを使う
子どもによって書きやすいマス目の大きさが異なるため、書きやすい大きさのマス目のノートを見つけてみてください。
協調運動が苦手な場合の練習方法
・手で空中に文字を書く「空書き」をする
書きやすい文房具を使う方法
・文字を書きやすいよう、しっかり握れる「三角鉛筆」や、芯の柔らかい鉛筆などを使う
お子さまにできる合理的配慮
合理的配慮とは、障害のある人が障害のない人と同じように学んだり働いたりできるよう、一人ひとりの特徴や場面に応じて、社会が工夫や配慮をすることです。
ディスグラフィアのある子どもに対しては、以下のような配慮の例があります。
配慮を得たいときは、担任の教員に相談してみてください。
- 集中しやすいよう、前の方の席に座らせてもらう
- パソコンやタブレット端末などのデジタル機器を活用する
- 黒板に書く事柄をあらかじめプリントにしておいてもらい、授業中はプリントを見ながらノートに書き写す
- 黒板に書かれた内容をノートに書き写す代わりに、タブレット端末などで撮影して写真で残す
専門機関でのトレーニング
ディスグラフィアがある場合は、児童発達支援事業所などの専門機関でトレーニングを受けることでも、困りごとの軽減が期待できます。
とはいえ、一人ひとりつまづきのポイントや困りごとの原因は異なり、お子さまのやる気が出る方法や適切な学び方もさまざまです。手段や方法論に着目してお子さまに合っていない方法を続けると、ストレスになったり、さらにやる気が低下してしまうこともあります。そのため、お子さま一人ひとりに合わせた指導をする事が重要です。
児童発達支援事業所・放課後等デイサービス・学習塾を運営するLITALICOジュニアでは、ディスグラフィアを含むさまざまな特性のある子どもにあわせた指導をおこなっています。
視覚・聴覚・体感・・・どんな学び方が理解しやすいかは人それぞれです。LITALICOジュニアでは、お子さまのスキルや特徴、得意・不得意・関心事を把握・分析し、その上で一人ひとりに合わせた学習計画を作成し、お子さまの特性や理解度に合わせて最適なプログラムを実施しています。
学習に関する指導の実績も豊富にあります。気になる方はお気軽にお問い合わせください。
ディスグラフィア(書字障害)についてまとめ

ディスグラフィアは「SLD(限局性学習症))」の種類のうちの一つで、文字や文章を書くことに困難が生じる症状のことです。
脳機能の偏りが原因だと考えられているため、書く練習をただくり返しても効果は期待できません。子どもの特徴に合った支援をおこなうことが大切です。
ご家庭での支援だけでは改善が難しいと感じる場合は、専門機関も利用してみてください。








