小学3年生の課題と指導事例
自立に向けた1歩を踏み出す学年!
友だち関係でのつまずきや学習面をサポート。

活動範囲や友だちとの関わりも広がる年頃。自我が確立されはじめ、自分でやってみたい・1人でできるといった考えを持つようになり、自立に向けた1歩を踏み出す時期です。同時に友だち付き合いが増え、集団で行動することも多くなり、友だちとのトラブルも増えてきます。
また学習面では、抽象的な内容を自分の中で具体化する練習をする学年です。
自主学習など自分から取り組む姿勢を育むとともに、相手の気持ちを理解し適切なコミュニケーションが取れるようにサポートしていきます。
発達支援のプロに相談しませんか?
お子さまの困りに合わせた相談ができます。
LITALICOジュニアでの課題別指導例
お子さまは一人ひとりつまづくポイントや得意な学び方がことなります。
お子さまに合わせた方法で指導プランをご提案しています。
課題1
字の読み書きが苦手
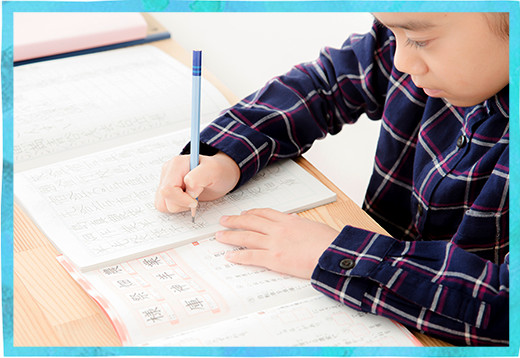
漢字を覚えるのが苦手。集中力がなく、字を読むのも書くのも得意ではないので、学年相応の学習についていけるか心配です。
指導事例
パーソナルコースの指導事例
漢字の覚え方と、集団で学習する姿勢を身につけていきます。
マンツーマンの授業で、まず自分に合った漢字の覚え方を見つけ、集団指導では読む練習をしながら、一斉授業に参加する姿勢を身につけていきます。
-
- マンツーマン指導/毎週
-
漢字が苦手なお子さまのの場合、漢字ゲームや漢字パズル、漢字を使って文章を作る、漢字のつくりでストーリーをつくる(春=三人で日なたぼっこをする春)、似た漢字を見比べて選ぶなどさまざまなプログラムから、本人にとって、一番楽しめる、学びやすい勉強方法を見つけながら学習します。
また、教科書より大きな文字で文章を読む、音読での息継ぎの箇所をチェックするなど、本人の特性に合わせて読みやすい工夫を探しながら学習します。
学習に集中できないときは、途中に休み時間を入れて、身体を動かし、感覚の刺激を満たしてから、学習に戻ると落ち着いて取り組めるようになります。
-
- 家庭での学習
-
漢字パズルやカルタや、クイズ番組など、楽しく学べる機会をうまく活用します。
また、読んだり、書いたりしたときに、できていないところを指摘するのではなく、できているところを褒める関わりをしていきます。
それにより、学習への意欲が維持され、自分から学習の工夫を取り入れられるようになっていきます。
- 家庭での学習
ポイント
読み書きが苦手なお子さまは、学習への負担感がないようにサポートしていくことがとても重要です。
本人が取り組みやすい雰囲気を作ったり、できていることを肯定したり、まずはできたところまででOKにして褒める、などの関わりにより、負担感を減らして、学習への拒否が起きないようにフォローしていきます。
発達支援のプロに相談しませんか?
お子さまの困りに合わせた相談ができます。
課題2
友だちとのやりとりが苦手

コミュニケーションが一方的で、相手の状況を考えずに言いたいことを話してしまいます。
指導事例
パーソナルコースの指導事例
会話の正しいやり方やルールを学びながら、同時に相手の表情や気持ちを理解する練習をおこないます。
-
- マンツーマン指導/毎週
-
会話のルールやマナーを理解するために、まずは動画でいい見本と悪い見本とを見比べてもらい、いいと感じるところ・よくないと感じるところをそれぞれ見つけてもらいます。
次に先生と会話のロープレをおこなって、先生からいい見本と悪い見本を見せます。実際によい見本と悪い見本を体感することで、理解を深めていきます。その後、いいと感じた会話のやりとりをお子さまがやってみます。必要に応じて、動画を取って、自分がどのような会話をしているのか客観的にも振り返れるようにします。
-
- 家庭での学習
-
会話のルールやマナーをご家庭で、保護者さまも一緒に取り組んでいただきます。保護者さまがルールに合わせた会話の見本を見せることで、お子さまが日常場面での、会話のスキルをより発揮しやすくなります。
「今の声かけ、相手の気持ちを考えながら伝えてくれていたね」など、できているところを具体的に褒めて振り返るようにします。
ポイント
コミュニケーションスキルの習得手順は基本的に、まずは座学(ワークブックや本等)を学び、その後、できている人の実践を見て真似ます。できている人の見本を見た後は、実際に先生を相手にロープレをおこない、都度、「できているところ、難しかったとこと、どうしたらできるようになるか」振り返りをおこないながら、お子さまの成長は加速していきます。
発達支援のプロに相談しませんか?
お子さまの困りに合わせた相談ができます。
課題3
集団行動の中でルールが守れない

相手の気持ちを汲み取るのが苦手で、友だちとコミュニケーションがうまく図れずにケンカとなり、集団から孤立してしまうことが多いです。
その言動で、なぜ友だちが怒るのか、イメージするのが難しいようで、傍からみると自分勝手と思われがちな行動が多く、友だちとのトラブルにつながることがあるので、もう少し相手の気持ちを想像して、自分の言動を変えられるといいなと思っています...。
指導事例
パーソナルコースの指導事例
友だちとの交流が盛んになってくると、集団の中でのルールやマナーを理解して守ることが円滑なコミュニケーションに必要となります。
自他の意識も芽生えてくる時期だけに、トラブルが続くことにより劣等感や不登校につながってしまうこともあるため、本人にとって分かりやすいルール理解の仕方や、覚え方を見つけていきます。
-
- マンツーマン指導/毎週
-
困ったり嫌な気持ちになったりしたときに、自分のイライラの状態、先生や友達への説明の仕方や伝え方が分からないため、集団活動の中でトラブルになる場合が多いです。
まずは、先生とゲームをする中で、イライラしてきたときに、イライラメーターを使って、イライラ60%のときの自分の気持ち、70%のときの自分の気持ちを認知します。
その後、何%になったら、何をすればいいかを一緒に考えていきます。
「何をすればいいか?」の手立てを考える中で、先生や友達に自分の状況を伝える練習もしていきます。
それにより、イライラが少ないうちに、先生や友達に声かけをして、困りを解決していくスキルを身につけていきます。
-
- 家庭での学習
-
家庭内でもイライラメーターを使用していただき、〇%になったらこれをやる、というルールを決めておきます。保護者さまや他のご兄弟も一緒に取り組んでいただくことでイベントのような形で取り入れやすくなります。また、保護者さまやご兄弟がイライラしたときの手立てを、ご本人が知ることで、他の手立てを知ることができたり、「イライラすることは僕だけじゃないんだ、イライラは言ってもいいことなんだ」という安心にも繋がり、より家庭内でも取り組みやすくなります。
ポイント
集団行動の苦手は、集団活動の中で練習をするイメージを持たれている方が多いですが、集団活動に参加が難しい苦手さは、むしろ個別で取り出して練習していく必要があります。個別と集団の違いは、先生の声かけの多さ、周りからの刺激量の多さです。まずは個別で先生の声かけを多く、刺激を少なくしながら、最も身につけたいスキルを習得していき、徐々に、先生の声かけを減らしたり、刺激の量を増やしながら、個別の中で、集団で応用できるようにステップアップして練習をしていくことで、失敗せずに集団活動の中に入ることができるようになります。
発達支援のプロに相談しませんか?
お子さまの困りに合わせた相談ができます。
まとめ
友だちと自分の関係に意識が向きやすい小学校3・4年生は、自他の違いが浮き彫りとなる時期です。コミュニケーションの幅や言葉のレパートリーが増えていく中で、もともとの苦手分野が表面化して、自分なりの解決策を模索し始めるときでもあります。
スムーズに集団生活を送るためにも、苦手とすることの背景要因を見極めて抽象的な物事への理解を具体化していくとともに、解決策へつなげていく視点をもつことが大切です。
そのためには、まず大人が適切な対処法を提示してお子さま自身が自分に合ったものを選べる環境を設定し、状況に応じた言動のレパートリーを増やしていきましょう。
また、先生や保護者など周囲の大人が情報を共有して、お子さまに気づきを促す言葉がけをするなど、できた・成功したという経験を積み重ねていけるよう導いていきましょう。









小学3年生の発達の目安
・今日の予定を意識して行動する
・あまりのあるわり算ができる
・絵や写真を説明する文章を書くことができる
・ルールや手順が複雑な活動を理解し参加することができる
・周囲の状況からそれぞれの感情を推測してふるまいを変えられる