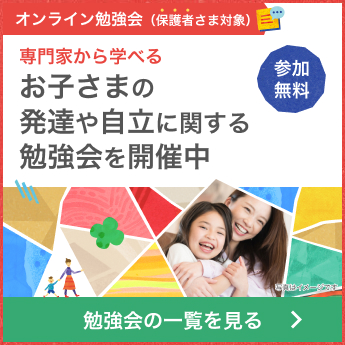特別支援学校は、障害のある子どもが就学先として選べる選択肢のうちのひとつです。
しかし、「名前は聞いたことがあるけれど、具体的にどのような教育をしているの?」「養護学校との違いは?」「発達障害のある子どもは入学できるの?」など、さまざまな疑問を抱いている方も多いのではないでしょうか。
今回は特別支援学校の対象者や入学条件、授業内容、養護学校との違いなどを解説していきます。
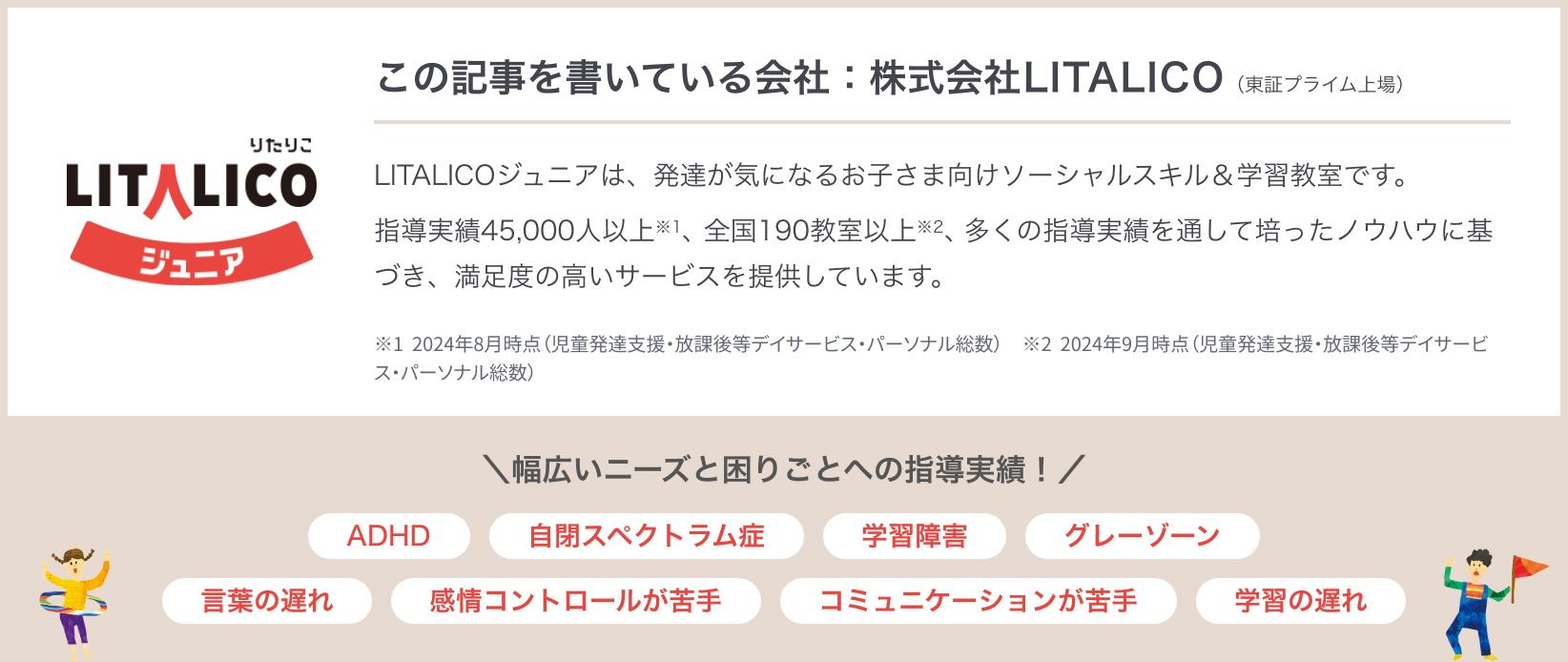
特別支援学校とは

特別支援学校とは、心身に障害のある子どもたちが通う学校のことです。障害の特性などを参考に、一人ひとりに合わせた授業が行われるといった特徴があります。
令和4年度(2022年度)のデータによると、幼稚部・小学部・中学部・高等部を合わせて、全国に約1,055校設置されています。
文部科学省のWEBサイトによると、特別支援学校の目的は「障害のある子どもに対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習や生活の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けること目的とする」と記載されています。
具体的な授業内容は後の項目で解説していきます。
特別支援学校の種類や養護学校との違い
特別支援学校のほかにも「ろう学校」や「養護学校」などの言葉を聞いたことがある方もいると思います。障害ある子どもの学校としての文脈で使われることが多く、「特別支援学校とどう違うの」と気になる方もいるのではないでしょうか。
結論としては、それらは以前使用されていた名称で、現在は「特別支援学校」に一元化されています。
以前は特別支援学校は下記の3つに分かれていました。
- ろう学校(聴覚に障害のある子どものための学校)
- 盲学校(視覚に障害のある子どものための学校)
- 養護学校(肢体不自由や知的障害、病弱などの症状がある子どものための学校)
上記のように障害によって入学できる学校に違いがありました。それを2007年から複数の障害種別を対象とする特別支援学校に統一されたという流れがあります。
しかし、特別支援学校に一本化されているものの、名称が現在も「〇〇養護学校」のままとなっている学校も多くあります。
このことから、「養護学校と特別支援学校の違いはあるのだろうか?」と疑問に思われる方もいらっしゃいますが、「〇〇養護学校」も特別支援学校の中に含まれると考えておくといいでしょう。
特別支援学校の入学条件は?
特別支援学校は誰でも入学できるわけではなく、障害の種別や程度などによって入学条件が定められています。
特別支援学校の対象となる障害種別は以下の通りです。
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 知的障害
- 肢体不自由
- 病弱・身体虚弱
さらに障害の程度にも入学するための基準があります。
視覚障害
両目の視力がおおむね0.3未満の方や、視力以外の視機能障害があり、拡大鏡(虫眼鏡やルーペなど)を使っても、文字や図形を視覚で認識することが難しい方。
聴覚障害
両耳の聴力レベルが、おおむね60デシベル以上の方で、補聴器などを使っても、通常の話声を理解することができない、もしくは困難な方。
知的障害
- 知的発達の遅滞により、他者との意思疎通が難しく、日常生活上で頻繁に援助が必要な方。
- 知的発達の遅滞の程度が上記の1の程度に達しない方のうち、社会生活への適用が難しい方。
肢体不自由
- 肢体不自由の状態が、補装具を使用していても、歩いたり書いたりなど日常生活における基本的な動作が不可能もしくは難しい方。
- 肢体不自由の状態の程度が上記の1の程度に達しない方のうち、常に医学的観察指導を必要とする方。
病弱・身体虚弱
- 慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患、および神経疾患、悪性新生物、その他の疾患の状態が継続して医療、または生活規制を必要とする程度の方。
- 身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度の方。
発達障害のある子どもも対象になる?
上記のように、特別支援学校に「発達障害」の項目はありません。しかし、発達障害のある子どもでも特別支援学校の対象となる場合もあります。
まず、発達障害と知的障害が併存する場合は、先ほど紹介した知的障害の基準を元に特別支援学校の入学について判断していきます。
また、知的発達に遅れがなく、発達障害のみがある場合でも、「就学相談」の結果によっては、特別支援学校へ入学することもあります。
就学相談とは、障害のある子どもが、通常学級・通級・特別支援学級・特別支援学校のうち、どのような環境で学ぶのが良いかを相談しながら決めていく場のことです。
ただし、教育相談によって自動的に就学先が決められるわけではなく、本人や保護者の意志を最大限に尊重したうえで最終的な就学先を決定していきます。
教育相談の流れや名称は自治体によって多少異なりますので、詳しいことはお住いの自治体のホームページなどをご確認ください。
特別支援学校の授業内容

ここでは特別支援学校の授業内容を紹介します。
子どもに合わせた教育の実施
特別支援学校は子ども一人ひとりに合わせた教育がしやすい体制がとられています。
例えば特別支援学校のクラスは、
小学部および中学部:1学級あたり6人
高等部:1学級あたり8人
と少人数制になっていて、先生の目が届きやすいと言えます。
自立活動
特別支援学校では学習指導要領も別途作成されていて、その中に「自立活動」という特別支援学校独自の取り組みがあります。
自立活動とは、児童(生徒)が、自立を目指し、障害による学習上や生活上の困難を改善・克服するための指導時間のことです。
一人ひとりの障害の特性や状態に合わせて「個別の指導計画」が作成され、設定した目標を達成できるように指導がおこなわれます。
また、自立活動の内容は、6区分(27項目)に分けられています。
- 健康の保持
- 心理的な安定
- 人間関係の形成
- 環境の把握
- 身体の動き
- コミュニケーション
例えば、「人間関係の形成」の中には「他者とのかかわりの基礎に関すること」、「コミュニケーション」の中には、「コミュニケーション手段の選択と活用に関すること」などの項目が含まれています。
障害の特性に合わせた教育や配慮
障害の特性に合わせた教育とはどのような内容なのか、障害の状態ごとにご紹介します。
視覚障害
小学部や中学部では、小学校や中学校と同じ学習内容を、視覚障害への配慮を得ながら学ぶことができます。
例えば、弱視の子どもが授業を受ける場合、見えやすいように対象を拡大したり、白黒反転させた教材を使用したりしています。
目が見えない子どもの場合は、点字の読み書きをしたり、触ることで物の特徴を理解したり、においや音などから、周囲の様子を伺ったりする学習を行います。
また、白杖(はくじょう)を使って歩く力や、コンピューターを使い幅広い情報を得る力を身につけられるような指導を受けることもあります。
聴覚障害
小学部や中学部では、小学校や中学校に準ずる学習や、書き言葉の習得などを行います。それとともに、発達段階に応じて、社会参加を見据えた、手話や指文字などの指導も受けられます。
また、特別支援学校には、発音・発語指導のための鏡や補聴援助機器、オージオメータ(聴力を測定する機器)などが揃っていることも多く、学びやすい環境が整っています。
知的障害
一人ひとりの発達の状態や特性に合わせて、実際の生活場面を通しながら、生活に役立つ内容を学習します。
例えば、「自分の意思を伝えること」や、「日常生活における行動」について、継続的かつ段階的に学んでいきます。
また、特別支援学校にもよりますが、高等部には、普通科だけでなく職業教育(職業につくための知識や技能を学ぶ)を主とする学科が設けられていることもあります。
肢体不自由
一人ひとりの状態を考慮した上で、小学校や中学校などに準じた教育を行っています。
また、コンピューターや、視聴覚教材(視覚や聴覚に直接うったえかける教材のこと)などの教材や器具を活用しながら、個別指導やグループ指導をすることを重視しています。
さらに、環境面では「手すり・スロープ・エレベーターなどの設置」や「廊下は車椅子がすれ違える広さにしてある」など、子どもが可能な範囲で自らの力で学校生活ができるように整備されています。
病弱・身体虚弱
病気の状態などに配慮しながら、小学校や中学校などとほぼ同じ学習を行います。
長時間の学習が困難な子どもに対しては「学習時間を短くする」など、一人ひとりに合わせて、柔軟に対応します。
また、自立活動の時間には、子どもが病気への不安感を抱いたり、自信を喪失したりすることに対して、メンタル面の健康維持をするための学習もしています。
特別支援学級と特別支援学校の違いは?
障害のある子どもが学べる環境として、特別支援学校のほかに特別支援学級があります。
名称が似ていることから、「両者の違いがよくわからない」という方もいると思います。
この項目では、まず、特別支援学級がどのような場所であるのかを解説した後、特別支援学校との違いをご紹介します。
特別支援学級とは?
特別支援学級は、小学校や中学校の中に設置されている学級(クラス)のことです。
文部科学省のWEBサイトには、「小学校・中学校において、障害のある子どもに対して、学習上または生活上の困難を克服するために設置される学級」と説明があります。
学級は障害種別ごとに下記の7つに分かれています。
- 自閉症・情緒障害
- 知的障害
- 肢体不自由
- 弱視
- 難聴
- 言語障害
- 病弱者および身体虚弱
普段、授業を受けるのは特別支援学級の中ですが、タイミングによっては通常の学級の子どもたちと時間を共にすることもあります。
1学級あたりの生徒数の基準は8人と、少人数制である点も特徴です。
特別支援学校との違い
ここでは特別支援学校と特別支援学級の違いについて紹介します。
まず違う点として、通常の学級の生徒との交流があります。
特別支援学級は、小学校や中学校の中にあるため、自然と他クラスの子どもと触れ合う機会が増えると考えられます。実際に、学校行事や給食などの時間を共有することもあります。
特別支援学校でも、交流および共同学習の場は設けられていますが、小中学校の中に設置されている特別支援学級と比べると、頻度は少なくなるでしょう。
次に違う点として、教員免許が必要かどうかということも挙げられます。
特別支援学校の場合、教員になるためには、通常の「教員免許」に加えて「特別支援学校の教員免許」を取得している必要があります。
なかには「特別支援学校の教員免許」を持っている教員もいますが、現状の制度上では必須ではありません。
特別支援学校と特別支援学級以外の選択肢
特別支援学校と特別支援学級の違いを紹介しましたが、ほかにも障害のある子どもが受けられる教育の選択肢があります。ここでは「通常学級で合理的配慮を受けながら学ぶ」と「通級に通う」方法を紹介します。
通常学級で合理的配慮を受けながら学ぶ
通常学級とは、大多数の子どもたちが通う学級のことです。
また、合理的配慮とは、障害のある方が、教育現場や職場などの社会生活において無理なく活動が続けられるよう、障害の特性や困りごとに合わせて実施される配慮のことです。
教育現場での合理的配慮の例としては、下記が挙げられます。
- 車椅子で移動できるように施設を整備する
- 障害の状況に応じて専門性のある教員を配置する
- 拡大版や点字版の教科書を用意する
- 情緒を安定させるための小部屋を用意する
- 口頭指導だけでなく、メモなどで情報を伝える など
この他にも、合理的配慮の種類は多数ありますが、学校によっても「対応できるかどうか」は異なります。合理的配慮を希望する場合は担任や学年主任、スクールソーシャルワーカーなどに相談してみるといいでしょう。
通級に通う
通級とは、通常学級に通いながら、障害に応じた指導を通級指導教室で受ける制度のことです。
例えば、週に何時間か通級による指導の時間だけ通級指導教室に移動して、それぞれの困りごとや課題に合わせた支援・指導を受けることができます。
指導の内容は「特別支援学校学習指導要領」の「自立活動」に相当し、子どもの特性や困りごとに合わせておこなわれます。
また、在籍する学校に通級指導教室がない場合は、ほかの学校の通級指導教室に行って指導を受けることもあります。
特別支援学校への入学の流れ

ここでは特別支援学校への入学の流れを紹介します。自治体や入学先の学校によって多少異なることがあるかもしれませんが、参考にしてみてください。
就学相談
特別支援学校は障害の程度などの入学条件を満たせばだれでも入学できるわけではありません。就学相談を通して子どもにとってどの教育が適切かを検討し、本人や保護者の意思も尊重したうえで決めていきます。
就学相談は保護者からお住いの自治体の教育委員会に申し込みをすることで行えます。特別支援学校の小学部への入学を希望する場合は、前年の4月~6月に相談の申し込みをします。
地域によっても異なりますので、詳しく知りたい方はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
就学先の決定
就学相談を申し込んだ後は、保護者と担当者の面談、子どもの様子の確認、入学希望校の見学・体験、医師による診断などが行われます。
特別支援学校の見学や授業の体験は夏ごろに行われることが多く、実際に学校の雰囲気や授業の進め方が子どもに合っているか確かめることができます。
見学や体験の結果、就学先を決定した場合は教育委員会に入学を希望する旨を伝え、教育委員会から決定通知が送られてくるという流れです。
発達障害のある子どもが利用できる支援機関
発達障害のある子どもやその家族への支援としては「発達障害者支援センター」や「障害児通所支援」などがあります。
発達障害者支援センター
発達障害者支援センターでは、障害のある子どもや大人、その家族をサポートしています。
子どもの障害について相談できる機関としては、他にも児童相談所などがありますが、発達障害者支援センターの特徴は「発達障害」に特化している点です。
医療や教育など、関係機関と連携をとりつつ、さまざまな相談にのったり、助言をおこなったりしています。
ただし、発達支援センターによって、具体的な支援内容は異なります。
まずは、発達障害者支援センターの「発達障害者支援センター・一覧」ページから、お住まいの地域にある発達障害者支援センターを見つけて、どのような取り組みをしているのか、情報をチェックしてみましょう。
障害児通所支援
障害児通所支援とは、障害のある子どもが事業所に通いながら日常生活や集団活動などでの困りごとへのサポートを受けることができるサービスのことです。
未就学の子どもを対象とした児童発達支援や就学児を対象とした放課後等デイサービスなどがあります。
放課後等デイサービスでは授業の後の放課後や長期休みの際に通って、対人スキルや自分に合った学習方法、整理整頓、スケジュール管理などを身につけるプログラムを受けていきます。
発達の気になる子どもの学習塾
LITALICOジュニアは発達の気になる子どもに向けた学習塾を各地に展開しています。
LITALICOジュニアの特徴は「子どもが10人いれば、特性も10通りある」と考え、一人ひとりに合わせた指導を提供していることです。
- 言葉の遅れが気になる
- 友達とトラブルになりやすい
- 感情のコントロールが苦手
- 周りから学習で遅れをとっている
- 学習意欲が低い など
このようなさまざまな特性に合わせて、読み書きなどの学習や、ソーシャルスキル(社会の中で生活していくためのスキル)向上のための指導をおこない、子どもの成長をサポートしています。
LITALICOジュニアの教室は全国に100以上あり、これまで8,000人以上の子どもを支援してきた実績があります。
教室に通うことが難しい子ども向けに、オンラインでの授業も行っておりますので、ご興味ある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。
特別支援学校のまとめ

障害のある子どもが選べる就学先は、複数あり、特別支援学校もそのうちの1つです。
クラス編成が少人数制だったり、自立のための知識や技能を身につけられたりと、小学校や中学校では得られにくいサポートを受けられる点が特徴です。
他にも「特別支援学級」など、選択肢はいくつかあるため、「子どもに一番合った環境はどこか」迷ったときは、各支援機関へ相談したり、就学相談の場を活用したりしましょう。