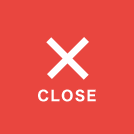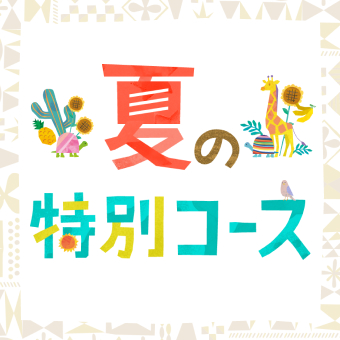この記事では、特別支援学級への進学・転籍を検討されている保護者さまから寄せられたお悩みについて、鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授である井上雅彦先生にご回答いただきました。
特別支援学級とは?

特別支援学級とは、小学校・中学校に設置されている障害のある生徒を対象にした少人数の学級です。
障害による学習や生活の困難を克服するために、自立活動や各教科を合わせた指導など特別な指導を、生徒のニーズに応じておこないます。
特別支援学級は通常の学級とは異なり、障害種別に学級が編制されます。
特別支援学級の種類
特別支援学級は、以下の7種類あります。
- 弱視
- 難聴
- 知的障害
- 肢体不自由
- 病弱・身体虚弱
- 言語障害
- 自閉症・情緒障害
ただし、特別支援学級を設置している学校であっても、7種類すべてが設置されているわけではありません。
そのため、就学を考えている学校にどのような種類の特別支援学級が設置されているのかを確認することが大切です。
※自閉症は、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)において自閉的特徴を持つ疾患が統合され、2022年(日本語版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりましたが、この記事では、文部科学省の表記のまま「自閉症」と記載しています。
特別支援学級に入る基準

文部科学省では、特別支援学級の対象者を「その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況、その他の事情を勘案して、特別支援学級において教育を受けることが適当であると認める者」としています。
さきほど紹介した7種類のそれぞれの障害に対して、対象者の詳細な判断基準が示されています。
また、特別支援学級に入る基準は、障害の有無や程度だけではなく、子どもそれぞれの状態や校内、地域の体制などをふまえて総合的に判断されます。
入学までの流れとしては、就学相談などを通じて本人や保護者の意志を尊重しながら、市区町村の就学支援委員会が総合的に判断し、最終的に就学先の設置元である教育委員会から決定の通知が出されます。
うちの子は特別支援学級の対象になる?通級指導教室とのちがい、進路の選び方のポイントについて専門家が回答!

ここからは子どもの発達に詳しい鳥取大学 大学院 医学系研究科 臨床心理学講座 教授である井上雅彦先生に、特別支援学級にまつわる質問にお答えいただきます。
Q:特別支援学級と通級指導教室の違いは何ですか?
A.
通級指導教室は、通常の学級に在籍し、週1回から週2回程度の取り出しによって支援を受けることになります。
これに対して、特別支援学級の場合は特別支援学級に在籍し、主な授業は特別支援学級で受けることが一般的です。
特別支援学級に在籍の場合も、通常の学級で授業を受ける場合もありますが、基本的に特別支援学級で受ける授業の割合が多くなる傾向があります。
Q:特別支援学級はどんな子が通っていますか?うちの子は発達障害の診断はなく、いわゆるグレーゾーンに該当しそうなのですが、対象になるのでしょうか?
A.
文部科学省では、特別支援学級の対象者を 「その者の障害の状態、その者の教育上必要な支援の内容、地域における教育の体制の整備の状況、その他の事情を勘案して、特別支援学級において教育を受けることが適当であると認める者」としています。
したがって、法令上は正式な診断がなくても入級することができます。つまり、基準を満たし、本人や保護者が希望すれば、特別支援学級に入ることができます。
ただし、入級の基準は自治体によっても異なり、一般的には医学的な診断が重視される傾向にあります。
Q:子どもは現在通常の学級に通っていますが、勉強についていけない様子があり、特別支援学級への転籍を考えています。特別支援学級に通うことでデメリットはあるのでしょうか?
A.
デメリットとしては、以下のようなことが考えられます。
- 自分の在籍する学校に該当する種類の特別支援学級がない場合は、新設を申請するなどの手続きが必要
- 年度途中での転籍はできない
- 通級指導教室に比べると、通常の学級の子どもとの触れ合いが少ない
- 合わないタイプの子どもが同じクラスにいて、トラブルになったりかえって学習が妨げられる場合がある
しかし、以下のようなメリットもあります。
- 少人数クラスで、子どもの発達や特性に合わせたカリキュラムで学習できる
- 給食や昼休み、ホームルームなどは通常の学級の子どもと触れ合うことができる
途中で学級を変える際の注意点としては、どのようなお子さまが通っているのか、自分の子どもに合いそうかなど見学や体験を十分にして、本人の意思を聞きながら決めることが大切です。
Q:現在保育園に通う年長の子どもがいます。保育園では加配の先生についてもらって生活をしていましたが、小学校ではどの進路先を選ぶのがいいのか悩んでいます。進路先を選ぶポイントはありますか?
A.
学びの環境や進路についての悩みも多くの保護者の方が抱えられているかと思います。
進路先を選ぶ際には、以下のようなことを試してみるのがいいでしょう。
- 実際に教室を見学する
- 保育園や就学先の先生と話し合う
- 検討している学校に通われている先輩保護者の話を聞く
- 教室の体験があれば参加し、子どもの意見を聞く
お子さまをよく観察し、お子さまにとって何が必要か、どのような環境で学ぶのがいいのか、ご家族で話し合って決断するのがいいでしょう。
Q:自閉スペクトラム症の子どもがいます。特別支援学級では、子どもに合った勉強や学校生活が送れるのではないかと思い希望しています。具体的にはどんな風に学校生活を送れるのでしょうか。
A.
まず、自閉スペクトラム症で、知的障害(知的発達症)の併存がない場合は、自閉症・情緒の特別支援学級の対象となります。知的障害(知的発達症)を併存している場合は、知的障害の特別支援学級の対象となる場合があります。
特別支援学級では、子ども1人ひとりに合わせた学習カリキュラムや子どもの特性に合わせたサポートを受けながら学校生活が送れます。これにより、発達障害のある子どもも、自分のペースで学習を進めることができ、学習の効果を最大限に引き出すことができるといえるでしょう。
また、個別のサポートを受けることで、子どもが自信を持って学習に取り組むことができ、学びの成功体験を得ることができます。
学校生活では、通常の学級の子どもたちと一緒に行事に参加することもあります。行事に参加する際には、以下のように特性に応じた配慮がされることがあります。
- 聴覚過敏のある子どものために、耳栓やノイズキャンセラーを用意する
- 落ち着いて参加できるように、今していること、これからすることを、写真・絵を使うなどして見通しをわかりやすく提示する
- 一時休憩できる場所を用意する
自閉スペクトラム症のお子さまの中には、 学校行事への参加や、その前後に不安定になるお子さまもいます。 しかし、特性に応じた適切な配慮をすることで、行事を楽しみ、行事を通して大きく成長することが期待できます。
発達が気になる子どもが通える教室「LITALICOジュニア」
LITALICOジュニアは、全国で幼児教室や学習支援教室、福祉サービスとして利用できる児童発達支援・放課後等デイサービスを運営しています。
LITALICOジュニアでは、学習への取り組みだけでなく、コミュニケーションスキルや気持ちをコントロールする方法、時間の管理の仕方など、さまざまな特性を持つ子ども一人ひとりに合わせて必要なスキルの獲得をサポートしています。
通常の学級、通級指導教室、特別支援学級、特別支援学級、とさまざまな進学先に通われているお子さまが利用されています。
LITALICOジュニアでは、保育所等訪問支援もおこなっています。通常の学級に通う場合でも、通所受給者証を取得することで利用できるサービスです。保育所等訪問支援では、保育所(保育園)や幼稚園、小学校など、お子さまが普段通っている施設に支援員が訪問し、お子さまが安心して過ごすことができる環境を、園・学校の先生方と一緒に考え、サポートします。
お子さまについて気になることがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ

この記事では特別支援学級にまつわるお悩みにお答えしました。
特別支援学級は、地域や学校によっても用意されているクラスなどが異なるので、気になることがあれば、まずはお住まいの市区町村の窓口でご相談ください。
LITALICOジュニアでも無料相談をおこなっているので、お子さまの発達について気になることがある方はお気軽にお問い合わせください。