お役立ちコラム
同じミスを繰り返す子どもへの理解と対応方法~発達特性を踏まえたサポートのヒント~
2025.07.24公開

「何度言っても同じミスを繰り返してしまう」「できるはずなのになぜできないの?」このような悩みを抱える保護者は少なくありません。
ひと口に「同じミスを繰り返す」と言っても、実はその性質によって内容が大きく異なります。
個別の動作や作業でのミス
計算間違い、漢字の書き間違い、ボタンの留め忘れ、食べ物をこぼすなど、個別の動作や作業で起こるミス
いくつかの手順を組み合わせる場面でのミス
片付けの手順が抜ける、宿題を最後まで完遂できない、複数の作業を同時に進められないなど、いくつかの行動を組み合わせる場面でのミス
取り組み方や進め方でのミス
テストで難しい問題から順番に解いて時間が足りなくなる、見直しを忘れる、時間のかかる方法を選んでしまうなど、やり方や手順の選択に関わるミス
子どもが同じミスを繰り返す背景には、注意力の特性、記憶の仕組み、感情的な要因、環境の影響、発達の特性など、様々な要因が複合的に関わっています。
そのため、「なぜできないの?」と原因を一つに絞り込もうとするよりも、ミスの性質を理解し、幅広い可能性を視野に入れてアプローチすることが重要です。
また、重要なのは、同じミスを繰り返すこと自体は誰にでも起こりうるということです。
学習過程においては、同じような間違いを繰り返すことは必ず生じるものであり、それを前提とした対応策を考えることが大切です。
目標は「ミスをなくす」ことではなく、「ミスをしてもすぐに立て直せる環境と仕組みを整える」こと。完璧さを求めるよりも、失敗から学び直す力を育むことで、子どもも保護者も安心して挑戦し続けられます。
本記事では、ミスの性質を踏まえながら、考えられる様々な要因を整理した上で、実践的な対応方法をご紹介します。
この記事を書いている会社:
株式会社LITALICO
LITALICOジュニアは、発達が気になるお子さま向けソーシャルスキル&学習教室です。
指導実績45,000人以上※1、 全国190教室以上※2、多くの指導実績を通して培ったノウハウに基づき、満足度の高いサービスを提供しています。
2024年8月時点(児童発達支援・放課後等デイサービス・パーソナル総数)
2024年9月時点(児童発達支援・放課後等デイサービス・パーソナル総数)
幅広いニーズと困りごとへの指導実績!
ADHD/自閉スペクトラム症/学習障害/グレーゾーン/言葉の遅れ/感情コントロールが苦手/コミュニケーションが苦手/学習の遅れ
同じミスを繰り返す要因として考えられること
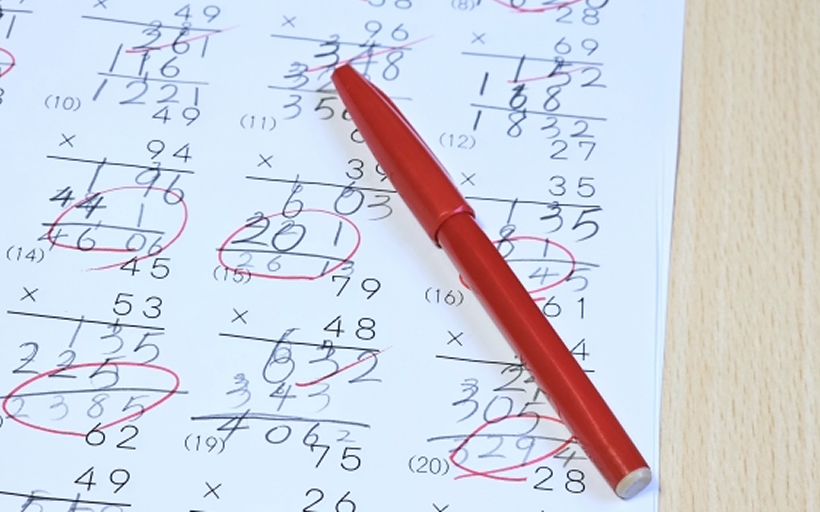
同じミスを繰り返す子どものほとんどは、意図的にそうしているわけではありません。本人なりに一生懸命取り組んでいるのに、結果として同じようなミスが起こってしまうのです。
もしも「あえて」同じミスを繰り返している場合でも、それには必ず理由があります。「なぜわざとやるの?」と問い詰めるのではなく、「どんな気持ちなのかな?」「何か困っていることはある?」と寄り添う姿勢で向き合うことが大切です。
以下では、同じミスが繰り返される様々な要因について詳しく見ていきましょう。
1. 誤った手順やパターンを覚えてしまっている(誤学習)
一度間違った方法を覚えてしまうと、同じミスを繰り返しやすくなります。例えば、漢字の書き順を間違って覚えた場合、正しい書き順を教えても、無意識に間違った書き順で書いてしまうことがあります。計算方法や字の形なども同様です。
これを「誤学習」といい、誤学習の修正は、新しく学習するよりも困難な場合が多く、そのためミスがなかなか改善されないことがあります。特に運動を伴う活動では、一度間違いが起こると自分では修正できず、不安や緊張と相まってミスが増幅することもあります。
2. 学習内容が定着していない(未学習)
学習内容が定着していない背景には下記3つの背景が考えられます。
わかる部分だけに反応してしまう
未学習の内容が多い場合、分かる部分だけに注目して判断してしまうことがあります。例えば、算数の文章題で「食べる」という言葉を見つけると、実際は足し算の問題なのに引き算で立式してしまうなどです。
流暢にできない→長く続かない
学習内容が十分に身についていないと、一つ一つの作業に時間がかかり、集中力が続かなくなります。
・完遂できない
時間がかかりすぎて最後まで取り組めない
・学習につながらない
例えば漢字ドリルで、本来一文字ずつ練習すべきところを、同じ画だけを連続して書くなど、効果的でない方法を選択してしまう
・早く終わりたくて確認が漏れる
疲れてしまい、確認作業を省いてしまう
援助要請が適切にできない
分からない場合でも一人で頑張ろうとしてしまう、学習が十分に定着していない状態で一人で頑張ろうとする、という行動でミスが生じる場合があります。
このように「分からない」「手伝って」と適切に援助を求めることができないために、間違った方法で取り組んでしまう場合があります。
3. 一連の活動の中でミスが生じている
正しい手順を習得し、学習内容はある程度定着しているように見えても、依然としてミスが続く場合には、一連の活動の中でミスが生じている可能性があります。
手順が長いことで生じるミス
複数の手順を踏む必要がある活動では、途中で注意がそれたり、手順を忘れてしまうことがあります。
・手順が抜けてしまう
長い手順の中で、途中の手順が抜けてしまうことで全体としてミスしてしまう場合になります。例えば、繰り上がりのある筆算で、繰り上がりの1を足し忘れる、などがこれにあたります。これには、流暢にできないことでワーキングメモリ(一時的に情報を保持する能力)の負担が大きくなることなどが関わってくる場合もあります。
・キーワードを抜き出せない
文章題から必要な情報やキーワードを抜き出せない、見つけられないなどの場合がこれにあたります。読むことの苦手さなどが関わっている場合もあります。
・注意がそれることで、完遂できない
長い手順の途中で他のことに気を取られることで最後まで完了できない場合があります。特にそれぞれの手順内に流ちょうにできないことが含まれていると生じやすかったりします。ミスというよりは、最後まで取り組めないことで解くことができていないケースがこれにあたります。
プランニングが難しい
「分かる問題から解く」といった戦略を立てることが苦手で、最初の難しい問題に時間をかけすぎて全体を完了できないなどのミスが生じます。
確認方法が確立できていない
検算や見直しといった確認の方法を知らない、または習慣化できていないことで、ミスに気づけない場合があります。
パターンへのこだわりが強い
「最初から順番に解きたい」といった特定のパターンにこだわることで、効率的な方法を選択できない場合があります。
【関連ページ】
4. 環境・感情の影響を受けている
不安、緊張
不安や緊張は、本来持っている力を発揮しにくくします。テスト場面での評価への不安、周囲からの過度な期待、新しい環境への緊張、疲労時などに生じやすく、特に運動を伴う活動では影響を受けやすくなります。
他にも、帰宅後に学校の宿題に取り組むときなどは、疲労やストレスなどが最も高まっているタイミングでもあるため、ミスなどが生じやすかったりもします。
環境
騒音、暑さ寒さ、視覚的な刺激の多さなど、環境の要因は誰にとっても活動を阻害し、ミスを生じさせやすくします。
注目引き
周囲の注意を引くために、意図的にミスをしている場合があります。ミスをした時に周囲の大人がより関心を向けてくれることを学習し、注目を引く手段として意図的にミスを繰り返してしまうことがあります。
回避
難しい課題や嫌な活動を避けるために、意図的にミスを選択する場合があります。
例えば、とりあえず何か書いて終わらせる、わざと間違えて早く終わらせる、体調不良を訴える、他のことに注意を向けるなどの行動が見られます。
5.発達特性との関連
いわゆる発達障害の診断基準にも特性から生じる困りについて関わるものが示されている場合もあります。
ただし、特性だけではなく、環境との相互作用の中でミスは生じるものですので、「同じミスを繰り返す=発達障害」というわけではなく、困りの程度によっても異なってきます。
以下は、診断基準に示されている特性の一例です。
ADHD(注意欠如・多動症)に関わる特性と困り
- 注意特性(不注意)に関わる見落としやケアレスミス
- 衝動性に関わる早とちりや確認不足
- プランニングの苦手さから活動や課題の完遂が困難
- 姿勢保持やじっと取り組むことの苦手さ(多動性)による集中や持続的な活動の困難
ASD(自閉スペクトラム症)に関わる特性と困り
- 音や視覚刺激への過敏など(感覚特性)による集中や持続の困難
- 同じパターンを繰り返してしまうことでによる反復的なミス
- 暗黙のルールや文脈の理解が困難なことから生じる困り
LD/SLD(学習症/限局性学習症)の特性と困り
- 読み書き計算の困難からくるミスや誤り
重要なのは、これらの特性の影響などを理解し、お子さんの得意・不得意を適切に把握することです。お子さんの特性に合った現実的な目標設定と支援方法を見つけることが大切です。
同じミスを繰り返してしまうときの対応方法

1. 環境を整える
学習環境は、お子さんの集中力や学習効果に大きな影響を与えます。まずは物理的な環境から整えていきましょう。
物理的環境の調整
お子さんが集中して取り組める環境を整えることは、ミスの軽減に直結します。集中できる環境作りには、いくつかのポイントがあります。
環境づくりのポイント:
- 集中しやすい静かな場所の確保
- 明るすぎない部屋・余分な刺激を減らす
- 不注意から必要なものを見つけられないを避けるために必要なものを事前に手の届く場所に準備
集中しにくい環境では、お子さんが「気をつけよう」と思っていても、同じミスを繰り返してしまいがちです。騒音や視覚的な刺激で注意が散ったり、道具探しで集中が途切れたりしないよう、環境を事前に整えておくことが大切です。
情報の整理
物理的な環境と同様に、お子さんに伝える情報もわかりやすく整理することが大切です。
効果的な情報の伝え方:
- 指示は短く、具体的に
- 視覚的な手がかりを活用(図表、色分けなど)
- 一度に多くの情報を与えない
例えば、「宿題をやりなさい」という抽象的な指示よりも、「まず算数のプリント1枚を解こう」という具体的な指示の方が、お子さんにとって分かりやすく、取り組みやすくなります。また、色分けされたファイルや図表を使うことで、視覚的に情報を整理できるため、理解が深まります。
2. 手順とルールの明確化
お子さんが「何をすればいいのか分からない」状態では、ミスが起こりやすくなります。明確な手順とルールを設定することで、迷いを減らし、スムーズな取り組みを促すことができます。
チェックリストの活用
「やるべきこと」を見える化するチェックリストは、非常に効果的なツールです。
単に項目を書き出すだけでなく、お子さんが主体的に関わることで、より継続しやすくなります。
チェックリストを活用するときのポイント:
- 子どもと一緒にやるべきことを箇条書きにしてみる
- 完了したら✓をつける(必ずできたことをほめる、うまくいったことを共有する)
できるようになってきたら…
- チェックをセルフチェックのみにしていく
- 子ども自身でチェックリストを作成して活用する(何をチェックリストにしたらいいかも考えてもらう)
最初は保護者がサポートしながら作成し、慣れてきたら徐々にお子さん主体で作ることで、「やり忘れ」や「手順の抜け」といった同じミスを防ぎやすくなります。チェックを入れる度に達成感が生まれ、継続への意欲も高まります。
ルーティンの確立
毎日同じ手順で取り組むことは、お子さんにとって安心感をもたらします。予測可能な環境の中では、集中力も持続しやすくなります。
効果的なルーティンの例:
- 決まった手順で取り組む習慣をつける
- 「準備→実行→確認」のサイクルを定着させる
- 時間を区切って取り組む
例えば、「机の上を片付ける→必要な道具を準備する→課題に取り組む→見直しをする→片付ける」といった一連の流れを習慣化することで、自然とミスの少ない取り組みができるようになります。
3. 記憶と注意のサポート
お子さんの記憶や注意力には個人差があります。それぞれの特性に合わせたサポートを提供することで、ミスを減らすことができます。
視覚的な手がかりの活用
「覚えておく」ことに頼りすぎると、どうしてもミスが生じやすくなります。目で見て分かる工夫を取り入れることで、記憶の負担を軽減できます。
具体的な工夫例:
- 付箋やメモの活用
- カラーペンでの色分け
- 図やイラストでの説明
例えば、算数の問題を解く際に「①問題を読む ②大切な数字に○をつける ③式を立てる ④計算する ⑤答えを確認する」という手順を付箋に書いて机に貼っておくと、毎回同じ手順で取り組むことができます。
繰り返し練習と流暢性の向上
「練習すれば上手になる」というのは確かですが、効果的な練習方法があります。ただやみくもに繰り返すのではなく、計画的に取り組むことが大切です。
速度と正確性を両立させる練習
漢字の読みや計算などの基本的なスキルでは、「正確にできる」だけでなく「速く正確にできる」ことを目指す流暢性訓練が効果的です。研究では、時間を区切った練習(タイムトライアル)をおこなうことで、単に正確性だけを重視した練習よりも、スキルの保持力や他の学習への応用力が高まることが示されています。
効果的な練習の進め方
- 短時間集中練習:1分程度の時間を区切った集中練習を複数回おこなう
- 即座のフィードバック:間違いがあったらすぐに修正し、正しい方法を確認する
- 段階的な難易度調整:正確にできるようになったら、速度も意識した練習に移行する
このような流暢性を重視した練習により、お子さんは基本的なスキルを「意識しなくてもできる」レベルまで身につけることができ、より複雑な課題にも集中して取り組めるようになります。
小さな「できた!」の積み重ねが、お子さんの自信と学習効果の両方を育てます。
4. 動機づけと自信の向上
小さな成功の積み重ね
「できた!」という体験を増やすために、達成可能な目標を設定し、結果だけでなく過程も評価することが重要です。
効果的なアプローチ:
- 達成可能な目標設定
- 過程も評価する
- 努力を認める声かけ
「今日は最後まで集中できたね」「前回より丁寧に書けているね」といった具体的な声かけで、お子さんは「頑張ることに意味がある」と感じるようになります。
興味関心を活かす
どんな学習や練習も、お子さんの「やってみよう」という気持ちがなければはじまりません。お子さんの興味関心を活かして、まずは「好き」「楽しい」という気持ちが芽生える工夫が大切です。
工夫の例:
- 子どもの好きなことと関連付ける
- ゲーム要素を取り入れる
- 選択肢を提供する
5. 効果的なツールの活用
視覚支援グッズ
- カラーインデックス付きファイル:教科や重要度で色分け
- マグネット式ホワイトボード:手順や注意点を常に見える場所に
- タイマー:集中時間と休憩時間を視覚化
整理整頓グッズ
- ラベリングシステム:「宿題」「提出物」など用途別に分類
- 透明な収納ボックス:必要なものがすぐに見つけられる
- 区切り板付きの筆箱:消しゴム、鉛筆など定位置を決める
指導事例:自分に合った対処法を見つけて成功体験を積む

小学校6年生のAくんは、忘れっぽさや計画通りに物事を進められないことで、学校の先生や保護者から叱られることが多い状況でした。本人も「また同じことで怒られてしまう」ということは理解していましたが、どのように対処すればよいのか分からず、結果として同じミスを繰り返してしまっていました。
支援の構造
1. うまくいく方略を見つける
まず、Aくん自身が自分の行動を客観視できるよう、先生と一緒にうまくいった場面とそうでない場面を振り返る習慣をつけました。その上で、改善策や代替案を本人が取り組みやすい順番に整理し、実際に試してみるというサイクルを繰り返しました。
2. お子さんの好き・楽しいを活かして、その方略を繰り返しやすい学習機会を作る
Aくんは興味のあることには一生懸命取り組める特性があったため、机上のプリント学習だけでなく、動画編集や好きなアイドルの紹介ページ作成など、多様な活動を通じて振り返りのスキルを身につけていきました。
特に効果的だったのは「工夫を考えるヒントシート」の活用です。
興味のある活動に取り組む前に「一緒に助け合いたいから、お互いの苦手を共有して、どうしたらうまくできるか考えよう」と先生がポジティブに声をかけながら、自分の苦手ポイントを整理する時間を設けました。

3. 苦手ポイントで方略をブラッシュアップする
Aくんが見つけた工夫を、実際の苦手な場面(忘れ物、計画実行など)で試してみることで、より実用的な方略へと改善していきました。うまくいかない部分は再度見直し、Aくんに合った方法へと調整を重ねました。
4.成功体験が増え、家庭でも工夫を活用できるようになった
この取り組みを続けることで、Aくんは自分に合った工夫を見つけることができ、プログラム内での実践だけでなく、家庭でも取り組めることを決めて継続するようになりました。その結果、家庭で褒められる場面が増え、本人も「自分なりの工夫が分かった」「うまくできた」という成功体験を積むことができ、とても嬉しそうに学習に取り組むようになりました。
まとめ

同じミスを繰り返すことは、決して珍しいことではありません。重要なのは、その背景にある要因を理解し、子ども一人ひとりに合った対応方法を見つけることです。
「ミスをしない」ことを目標とするのではなく、「ミスをしても大丈夫な環境と仕組みを作る」ことで、子どもたちは安心して学習や活動に取り組むことができるようになります。
LITALICOジュニアでは困りごとは本人だけに起因するものではなく、本人と環境の相互作用によって生まれるものだと考えています。そのため、子どもに合わせたオーダーメイドの指導だけでなく、お子さまが日常生活で過ごしやすい環境をつくる方法も一緒に考えています。
「同じミスを繰り返す」「何度教えても覚えられない」「どう声をかけていいかわからない」と悩んでいる方はぜひ一度お問い合わせください。
【参考】
- 村上佳津美「注意欠如・多動症(ADHD)特性の理解」
- 藤岡徹「自閉スペクトラム症の認知機能」
- 山口県「合理的配慮のヒント① 落ち着いて過ごせる教室環境(学習環境)づくり」
- 荒井 みなみ,上野 佳奈子「音環境に着目した学童保育施設の現状と環境調整手法に関する研究」
- 松下浩之,園山繁樹「新規刺激の提示や活動の切り替えに困難を示す 自閉性障害児における活動スケジュールを用いた支援」
- 熊谷亮「学校臨床における質問紙・チェックリスト活用によるアセスメントを考える」
- 野田航,松見淳子「小学 2 年生の掛け算スキルの流暢性の向上を目指した 応用行動分析的指導の効果」
- 尾之上高哉,井口豊,丸野俊一「目標設定と成績のグラフ化が計算スキルの流暢性の形成に及ぼす効果」
- 野田航「応用行動分析学と学習指導」
- 飯島有哉,山田達人,桂川泰典「教師の主観的賞賛行動が生徒の学校生活享受感情および教師自身の ワーク・エンゲイジメントに与える効果プロセス」





